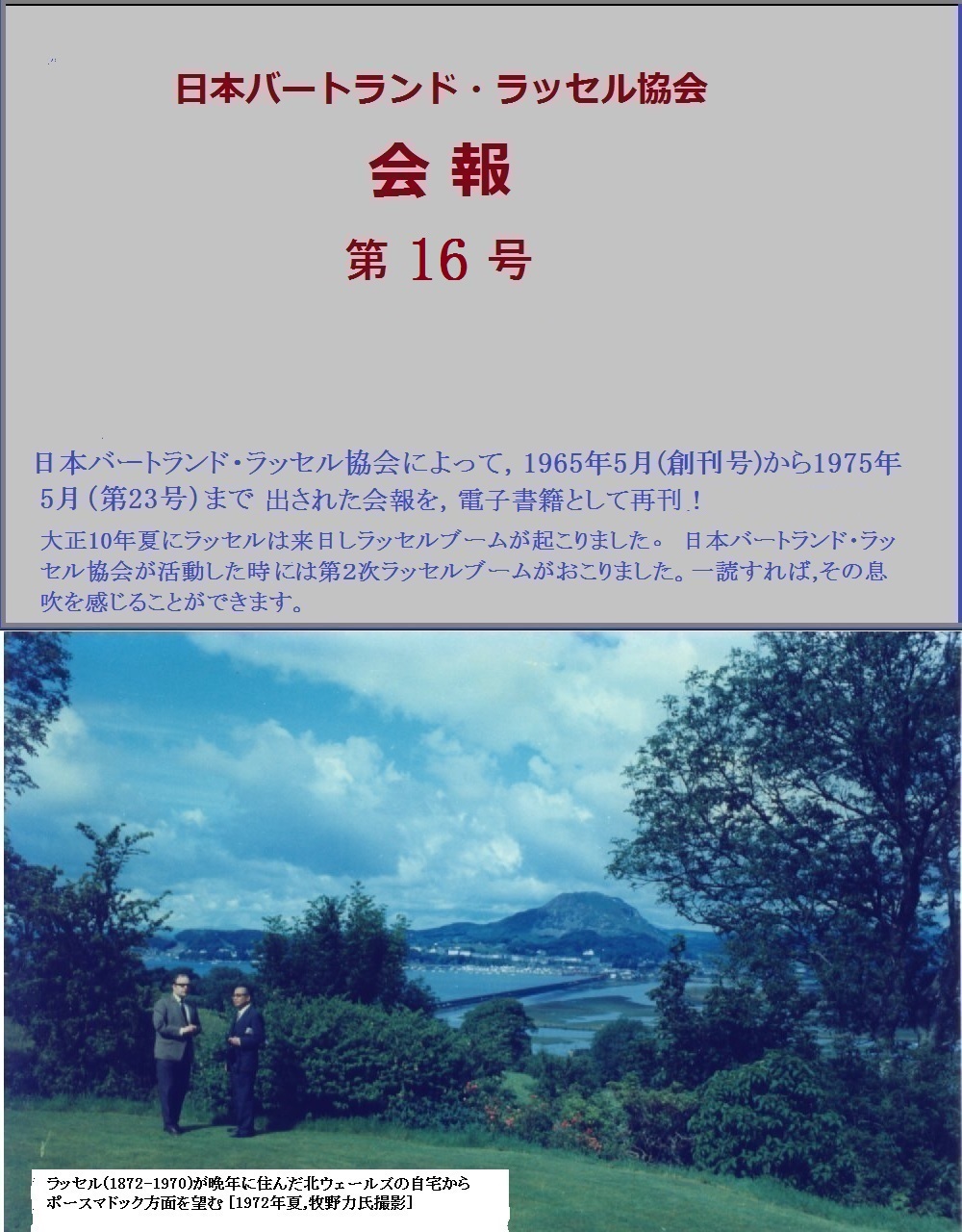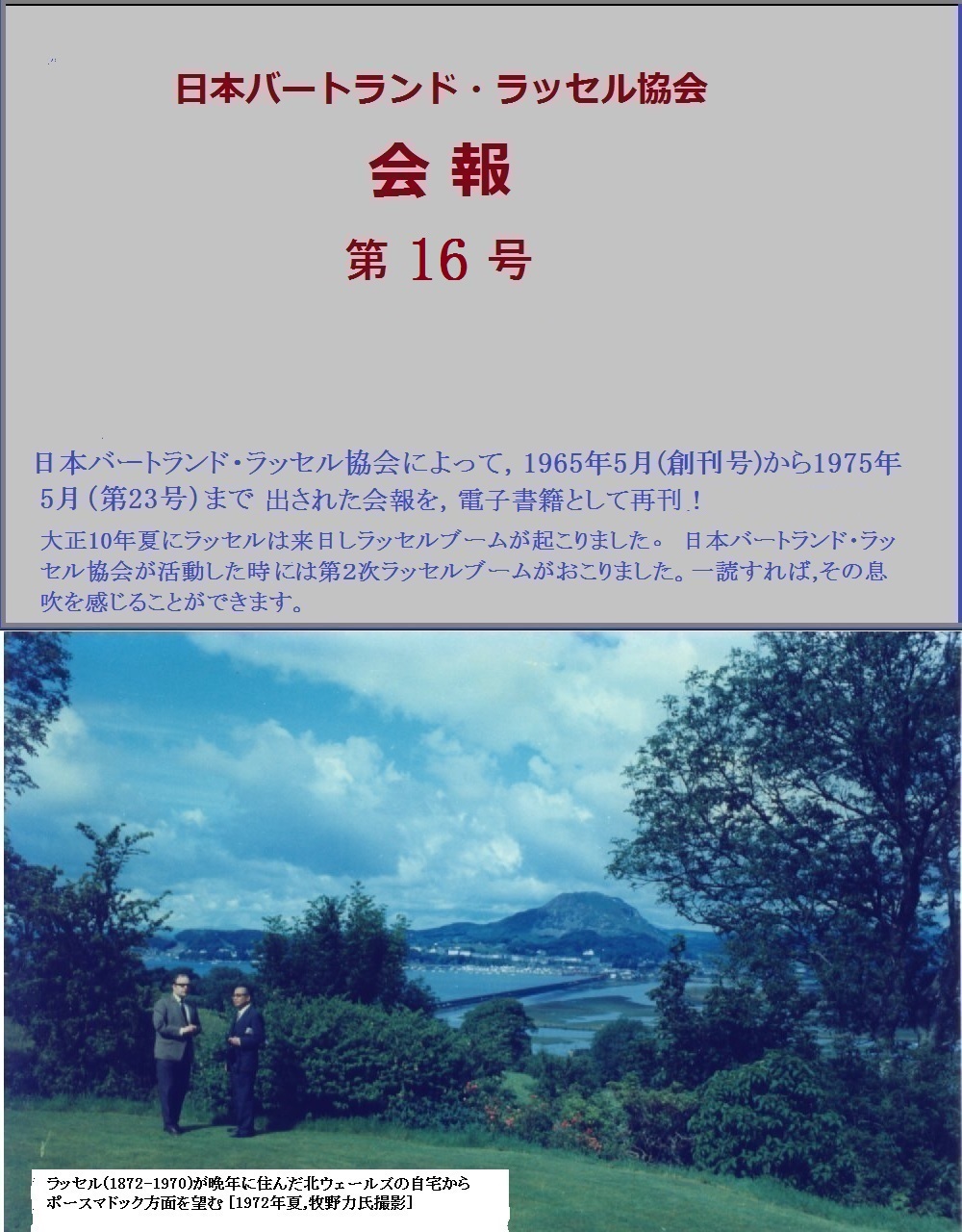長男と、つぎの女の子とをつれて散歩に出たとき、道角で、ひとりは右へ、ひとりは左へゆくことを主張したことがあります。このときも、「おとうさんのからだは二つにわけるわけにはいかないから、どちらへいくか、ふたりでそうだんして、きめなさい」と、まんなかに立って待っていたこともあります。わたくしのうちでは、こどもに「べんきょうしなさい」と言ったことがありません。これは、かなり努力のいることでして、こどもにも、それがわかったとみえ、長男は大学を卒業したときに「おとうさんは、いちども、ぼくに、べんきょうをせよとは言わなかったね」と感懐を述べました。「ウン」と答えただけですが、なんだか、むくいられたような気がしたものでした。