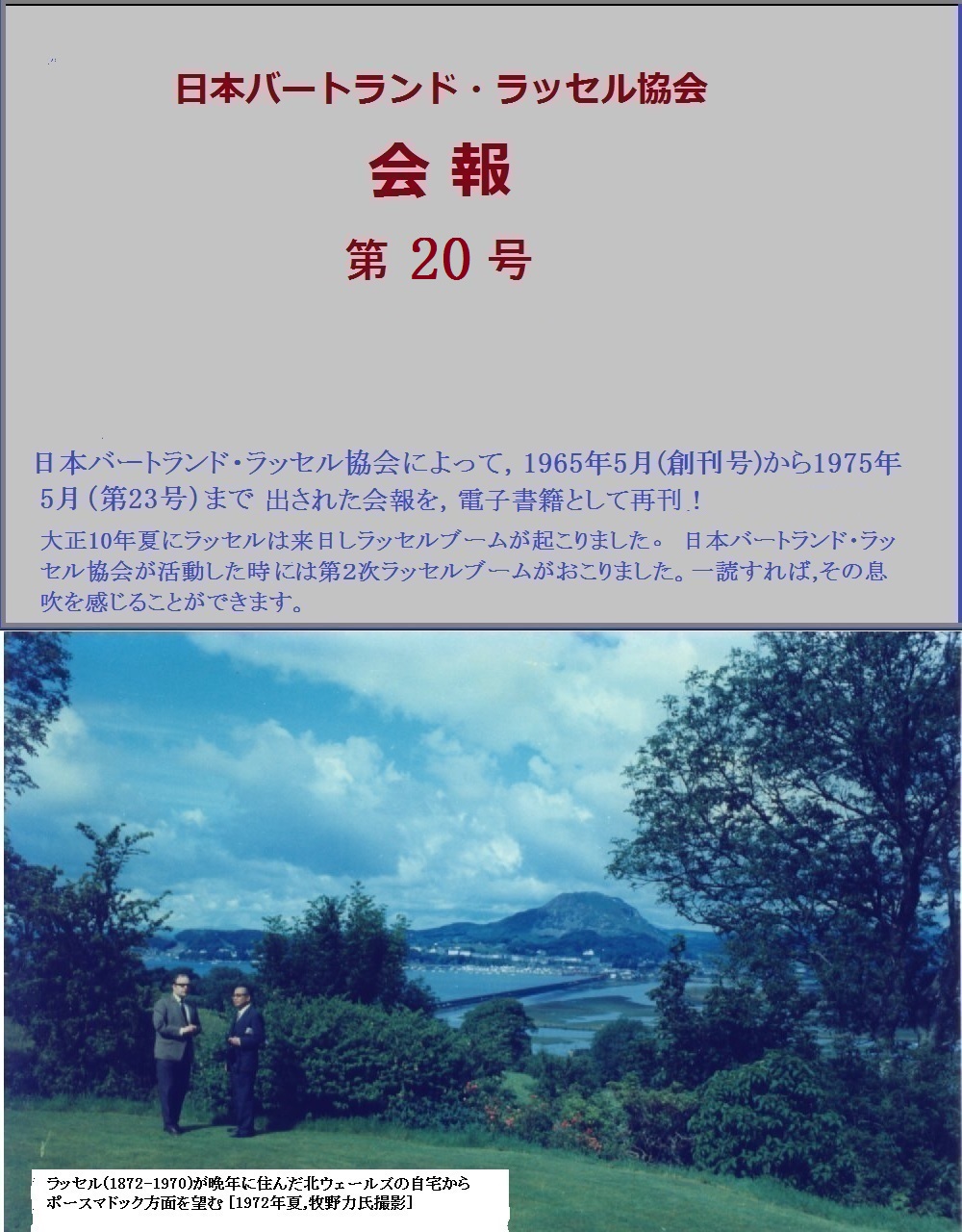バートランド・ラッセル著書解題19:ラッセル『外部世界はいかにして知られうるか』(石本新・解題)
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第20号(1972年1月)pp.6-11.
* ラッセル著書解題シリーズのn.19
* 石本新(1917~2005): 論理学及び哲学専攻/京大動物学科卒,総司令部,文部省勤務を経て,本論文執筆当時,東京工業大学教授
* 日本科学哲学会・石本基金の事業開始のお知らせ
 1.
1.
 この書物は数多くあるラッセルの哲学書の一つであるが,いろいろな意味において,ラッセル哲学展開の過程で大きな役割を演じている。まず第一に,この書物の出版後,ラッセル哲学はそれが敷設した軌道上を走ったのであって,その後のラッセル哲学が,「外部世界はいかにして知られうるか」から大きく離れたということはない。もちろん,このような解釈にはいろいろの反対意見もあろう。たとえば,この書物の次にまとまった哲学書として現われた「心の分析」(The Analysis of Mind, 1921)などにおいて採用された中性一元論と,その後におけるその放棄,また,「人間の知識」(Human Knowledge, its scope and limits, 1948)などにおいて示されたいくぶん操作主義的な見解などをふりかえってみると「外部世界はいかにして知られうるか」以後におけるラッセル哲学の不変性を強調しすぎてはならないのかもしれない。
この書物は数多くあるラッセルの哲学書の一つであるが,いろいろな意味において,ラッセル哲学展開の過程で大きな役割を演じている。まず第一に,この書物の出版後,ラッセル哲学はそれが敷設した軌道上を走ったのであって,その後のラッセル哲学が,「外部世界はいかにして知られうるか」から大きく離れたということはない。もちろん,このような解釈にはいろいろの反対意見もあろう。たとえば,この書物の次にまとまった哲学書として現われた「心の分析」(The Analysis of Mind, 1921)などにおいて採用された中性一元論と,その後におけるその放棄,また,「人間の知識」(Human Knowledge, its scope and limits, 1948)などにおいて示されたいくぶん操作主義的な見解などをふりかえってみると「外部世界はいかにして知られうるか」以後におけるラッセル哲学の不変性を強調しすぎてはならないのかもしれない。
しかしながら,この書物で展開された基本的構造ということになると,ラッセル哲学が変らないということはやはりまちがいのない事実なのである。そして,この構造こそラッセルが近代論理学から哲学の世界にもちこんで,ある程度成功を収めたラッセル哲学のもっとも大きな特徴なのである。この構造は,一口にいえば論理的原子論と称せられる一つの考え方であるが,その構造はラッセル哲学にとどまらずウィトゲンシュタインや論理実証主義の哲学にまで及び,しだいに薄れゆくとはいえ,現代哲学における大きな潮流の一つなのである。そして,この書物におけるあまりにも多彩な表現に眩惑されて,論理的原子論という導きの糸がこの書物を貫いていることを忘れてはなるまい。というわけで,「外部世界はいかにして知られうるか」は,通俗的な哲学入門書でもなければ,通俗科学の解説書でもない。わが国ではとかくこのような意味でしかこの書物が理解されてこなかったようであるが,実際は,ラッセル哲学の真髄が,それほど大部でもないこの書物のなかに圧縮された形で述べられているのである。それどころか,ある意味において西洋哲学におけるもっとも伝統的な問いに対するその当時としてはもっとも進んでいると同時にもっとも正統的な解答を与えようとする企てが,この「外部世界はいかにして知られうるか」のおもな意図なのである。わが国の哲学界においては,現在(=1972年)でもドイツ観念論の影響が強いために,ラッセル哲学がややもするとオーソドックスな哲学からはずれた異端的な哲学であると誤解されがちであるが,事実はその正反対であって,ラッセル哲学こそ西洋哲学の伝統をもっとも忠実に継承し,それを発展させた哲学であろう。
 では,「外部世界はいかにして知られうるか」を規定する構造とは何であろうか。いうまでもないことであるが,それは,ラッセルの数理哲学,すなわち数理論理学によって規定される構造である。ということは,一九一〇年から一九一三年,つまり,この書物が上梓される一年前に完成した「数学原理」(Principia Mathematica, 3 vols, 1910-1913)にもられている論理学が与える構造なのである。
では,「外部世界はいかにして知られうるか」を規定する構造とは何であろうか。いうまでもないことであるが,それは,ラッセルの数理哲学,すなわち数理論理学によって規定される構造である。ということは,一九一〇年から一九一三年,つまり,この書物が上梓される一年前に完成した「数学原理」(Principia Mathematica, 3 vols, 1910-1913)にもられている論理学が与える構造なのである。
しかしながら,ラッセルの論理学は,「数学原理」において突然発生したものではない。ラッセルの論理学の背景を知るためには,「幾何学の基礎に関する小論」(1897),「ライプニッッ哲学の批判的解説」(1900)などにはじまり,「数学の原理」(1903),「指示について」(1905),「階型理論にもとづく数理論理学」(1908)などを経て「数学原理」に及ぶ,いってみれば,前「数学原理」期におけるラッセルの全論理学が考慮されなければならない。さらに,それにとどまらず,ラッセル以前における近代論理学,とくに,フレーゲの論理学のこともまた忘れるべきではあるまい。このように考えると,一八七九年に出版されたかの記念すべきフレーゲの「概念文字」にはじまり,「数学原理」に終る近代論理学史における第一期をふりかえり,その近代哲学史上における位置づけを行なわなければならないことになろう。しかし,この方面の研究はわが国においてはもちろんのこと,ヨーロッパやアメリカにおいてもまだ緒についたばかりで,これといってまとまった研究もないし,また結論も出ていないのが現状である。ではあるが,「外部世界はいかにして知られうるか」を哲学史のなかで位置づけるためには,この時期における近代論理学の性格を一応概観しておくことがどうしても必要であろう。というのは,「外部世界はいかにして知られうるか」こそ,近代論理学における第一期の成果が,数理論理学という比較的せまい領域から,せきを切ってあふれ出て,哲学というより広い分野へ適応された最初の成果であるとみなすことができるからである。よくいわれることであるが,この書物は未完に終った「数学原理」第四巻の哲学的なスケッチであるともいえよう。
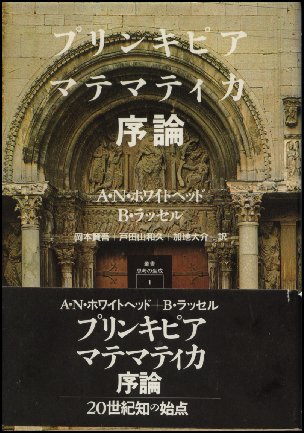 「数学原理」の第四巻がついに出版されなかった理由については,「数学原理」の共著者ホワイトヘッドとの間の意見の相違があげられているが,それはそれとして,この書物のあとに続く「心の分析」(1917)(松下注:1921年の間違い),「物質の分析」(1918)(松下注:1927年の間違い),「意味と真実性の探求」(1940),「人間の知織」(1948),さらに,ホワイトヘッドの「思考の有機化」(1917),「自然認識の諸原理」(1919),「科学的認識の基礎-自然という概念」(1920),「相対性の原理」(1922)などは,いずれも,「数学原理」の脚注であると同時に,哲学へのそのやや大ざっばな応用であると考えられよう。しかしながら,近代論理学第一期における業績が純粋培養のような形で論理学に極限されたアカデミックな研究室のなかで,ほかの分野との交流を一切たっていわば生産され,それが第一次大戦の直前に突如として哲学の領域に解き放たれ,その結果,「外部世界はいかにして知られうるか」にはじまる一連のラッセルやホワイトヘッド,あるいは,ニコーやカルナップの業績が生まれたのであると考えてはならない。そうではなく,フレーゲの「概念文字」にはじまり,「数学原理」でおわる第一期の近代論理学は,せまい意味における論理学の展開にとどまらず,同時に,哲学の場における運動であったということも否定できない事実なのである。したがってこの時期における近代論理学は,数学よりのところで近代論理学が展開されはじめた第一次大戦後に開始される近代論理学の第二期とはたいへん趣きを異にしているのである。いってみれば,フレーゲとラッセルによって象徴される近代論理学の第一期は,哲学と数学の蜜月時代であったといえよう。これに対して,ヒルベルトによって代表される第二期は,数学的関心が表面に出てきた時代であって,哲学との結びつきは,論理実証主義やポーランド学派によってかろうじて維持された時代であったといってよい。そして,ようやく最近になって,哲学的関心から近代論理学を積極的に利用しようという,いわゆる哲学的論理学がはじまりだしたというのが,最近の状況である。そして,その際,ラッセルの業績,とくに,「指示について」によって口火を切られた記述の理論が大きな話題となっていることは興味ぶかいことであろう。
「数学原理」の第四巻がついに出版されなかった理由については,「数学原理」の共著者ホワイトヘッドとの間の意見の相違があげられているが,それはそれとして,この書物のあとに続く「心の分析」(1917)(松下注:1921年の間違い),「物質の分析」(1918)(松下注:1927年の間違い),「意味と真実性の探求」(1940),「人間の知織」(1948),さらに,ホワイトヘッドの「思考の有機化」(1917),「自然認識の諸原理」(1919),「科学的認識の基礎-自然という概念」(1920),「相対性の原理」(1922)などは,いずれも,「数学原理」の脚注であると同時に,哲学へのそのやや大ざっばな応用であると考えられよう。しかしながら,近代論理学第一期における業績が純粋培養のような形で論理学に極限されたアカデミックな研究室のなかで,ほかの分野との交流を一切たっていわば生産され,それが第一次大戦の直前に突如として哲学の領域に解き放たれ,その結果,「外部世界はいかにして知られうるか」にはじまる一連のラッセルやホワイトヘッド,あるいは,ニコーやカルナップの業績が生まれたのであると考えてはならない。そうではなく,フレーゲの「概念文字」にはじまり,「数学原理」でおわる第一期の近代論理学は,せまい意味における論理学の展開にとどまらず,同時に,哲学の場における運動であったということも否定できない事実なのである。したがってこの時期における近代論理学は,数学よりのところで近代論理学が展開されはじめた第一次大戦後に開始される近代論理学の第二期とはたいへん趣きを異にしているのである。いってみれば,フレーゲとラッセルによって象徴される近代論理学の第一期は,哲学と数学の蜜月時代であったといえよう。これに対して,ヒルベルトによって代表される第二期は,数学的関心が表面に出てきた時代であって,哲学との結びつきは,論理実証主義やポーランド学派によってかろうじて維持された時代であったといってよい。そして,ようやく最近になって,哲学的関心から近代論理学を積極的に利用しようという,いわゆる哲学的論理学がはじまりだしたというのが,最近の状況である。そして,その際,ラッセルの業績,とくに,「指示について」によって口火を切られた記述の理論が大きな話題となっていることは興味ぶかいことであろう。
2
では,近代論理学の第一期を特徴づける思想とはいかなるものであろうか。一言にしていうならば,それはプラトン的実在論である。論理学や数学に話しを限っていうならば,論理学や数学を,われわれの主観とは無関係に予め存在する真理とみなそうという思想である。哲学の専門家でない人には,このようなことが何故ことさら問題にならなければならないのか不思議に思われるかもしれない。というのは,論理学や数学の法則はわれわれが勝手につくりだすものではなく,すでにあるものであるということは常識的な信念だからである。ここでは深入りする余裕がないが,主観的観念論として定義されるカント哲学の影響下においても,こういうプラトン的実在論が根本的に変ったようには思われない。そして,このような認識論こそ西洋哲学の正統派の考え方であるといえよう。
そして,近代論理学もこういった思想的雰囲気の中で孤々の声をあげたのである。すなわち,近代論理学の創始者フレーゲもこの点では当時,すなわち,十九世紀後半におけるドイツ哲学の多数派と意見を異にしていたわけではない。これについては,フレーゲに関してウィトゲンシュタインがものにした興味ぶかい思い出話しがあるから次に紹介しよう。
ウィトゲンシュタインは一九一〇年代の初めに英国からもどって数理哲学に方向変換すべくイエーナにフレーゲを訪問したことがある。その際,数が実在する対象であるという理論に問題がないかというウィトゲンシュタインの質問に対して,フレーゲは,「ときとして私は困難を感じますが,しばらくすると感じなくなります。」と答えている。フレーゲの示唆に従って,その後ウィトゲンシュタインはまもなくケンブリッジにいたラッセルのもとに赴くことになるのであるが,ひかえめではあるがフレーゲのこの発言はいろいろの意味において近代論理学の第一期を特徴づける発想であろう。つまり数はプラトン的なイデアとして'存在'している対象なのである(注:'実在'='存在'ではないことに注意)。
ここで忘れてはならないことは,このような実在論がフレーゲに限られるのではなく,ラッセルにもまたみられるということである。ラッセルがムーアとともに企てた観念論への反逆がいかなる文脈において行なわれたのか理解することは容易なことではないが,一九〇三年に現われた「数学の原理」執筆当時のラッセルが,フレーゲと同じぐらい,あるいは,それ以上に徹底した実在論者であったということは否定できないことであろう。また,その後に現われた主著「数学原理」もその技術的な側面の行間にフレーゲ式の実在論が顔をのぞかせているということは,多くの論者の一致して指摘するところである。実際,フレーゲの主著「算術の基本法則」も,「数学原理」もその目的は煎じつめれば,すでに存在している古典数学を再構成することにあるのであって,古典数学そのもののありかたを疑問視しているわけではない。そして,「数学原理」において階型理論に基づいて再構成された古典論理学が,その後ながくラッセル哲学を支配することになるのである。すでに述べたことであるが,ラッセルが「数学原理」に最後まで固執し,それに反する直観主義や構成主義の論理学にほとんど関心を示さなかったということは,ラッセルが晩年においてもある意味で実在論者であったことの証拠であろう。したがって意味づけ,あるいは,解釈ということを離れるならばラッセル哲学の構造は,「数学の原理」の哲学,いな,フレーゲの哲学ともそれほど変らなかったということがいえるだろう。
また,別の機会に述べたことであるが,「数学原理」に具体化されている論理学によって,ラッセル哲学が規制されているという事実も指摘しておく必要があろう。つまり,実在論にはちがいないが,その実在論が極端な形にまで走ることに対して,「数学原理」の論理学は歯止めの役割を演じているのである。
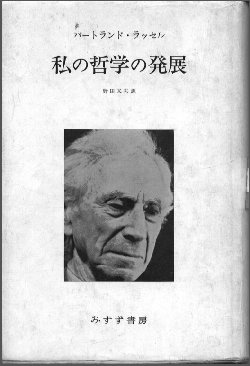 3
3
ではあるが,ラッセル哲学はその初期におけるフレーゲ式実在論にとどまっていたわけではない。ラッセル自身がその「私の哲学の発展」(My Philosophical Development, 1959)において刻明にあとづけているように,かの有名なピタゴラスからの退却がはじまるのである。プラトンといわずにピタゴラスといった理由は必ずしも明らかではないが,プラトンからの退却といってもさしつかえないであろう。そして,この退却がまず開始されたのが,「外界はいかにして知られうるか」においてである。もっとも,ラッセル自らがコペルニクス的とさえいっているこの書物で展開された方法も,実をいうと突如として考えつかれたというわけではない。そこにいたるまでには,ホワイトヘッドとの,またウィトゲンシュタインとの交流があったことを無視してはならない。また,ピタゴラスからの退却が「数学原理」で示されている枠のなかで行なわれているということも忘れてはなるまい。
では,いかなる退却が行なわれたのであろうか。一言にしていうならば,それは実在論の立場では存在するとされる対象を,論理的構成によっておきかえるという意味における退却である。カルナップがのちにラッセルのこの考えを極端にまでおしすすめて完成した「世界の論理的構築」(1928)(石本・藤川訳 東京図書)(注:原著は1928年に出版されているが,東京と書から邦訳が出ている記録が見つからない。出版の予定であったが,何らかの理由で中止になったのであろうか?)において引用しているラッセルの言葉に,「科学的哲学における最高の格言はこれである。すなわち,それが可能であるかぎり,論理的構成が推論される対象にとって代わらなければならない。」というモットーがあるが,それは,「外部世界はいかにして知られうるか」においても指針となっているのである。
ということは,具体的にはどういうことなのであろうか。たとえば,フレーゲにとってその存在を疑うことができなかった'二'(2)という自然数は,ラッセルの標語に従うといかなるものになるのであろうか。いうまでもないことであるが,フレーゲも分析されない形での'二'がそのままの姿で存在していると主張したのではない。のちに,ラッセルによって再発見されたフレーゲの定義によると,'二'という自然数は,すべての対の集合として定義される。この点に関しては,フレーゲもラッセルも全く同じである。ところが,このようにして構成された自然数'二'の,存在者としての資格ということになると,フレーゲと「外部世界はいかにして知られ得るか」におけるラッセルでは大きな意見の相違が生じてくる。フレーゲにとっては,このようにして構成された'二'は,それが構成された対象であるにしても,やはりプラトン的意味で実在する対象なのであった。これに対して,ラッセルにとっては,集合としての'二'の要素であるそれぞれの対を構成している各個物は存在しているが,それから論理的に構成された対,あるいは,自然数'二'は実在する対象というよりは,むしろ構成された論理的フィクションなのである。
同じことが,点や瞬間,さらに,空間についてもいえる。フレーゲはこのような対象については,十分意見を表明していないが,強いてフレーゲの考えを想像すれば,点や瞬間,また空間も,実在する対象であるということになろう。ところが,ラッセルにとっては,これらの対象は,フレーゲのいうように重々しく存在する対象ではなく,いってみれば,論理的に構成された軽い対象なのである。「外部世界はいかにして知られうるか」の言葉でいえば,やわらかいデータなのである。因みに,点や瞬間の論理的構成は,「外部世界はいかにして知られうるか」の第四章においてくわしく展開されている。
しかしながら,それぞれの存在者に与えられるウェイトの相違によって極端に実在論的なフレーゲの存在論とラッセルのそれが根本的に異るのであると考えてはならない。ラッセルがくり返し主張しているオッカムのかみそりによる大掃除にもかかわらず,多くの存在者はフレーゲのいうように,ほんとうに存在する存在者としてであれ,またラッセルがいうように論理的構成としてであれ,とにかく存在するのである。ということはフレーゲの存在論とラッセルの存在論が少なくともその構造においてはよく似ているということである。もっとも,フレーゲの論理学には階型理論がなく,ラッセルのそれは,この理論の支配下にあるのであるから,フレーゲとラッセルの論理学が類似していることを強調しすぎてはならないだろう。ではあるが,そのかもし出す雰囲気といったものは必ずしも異質のものではない。そして,「数学原理」によって代表されるこういった論理学をフレーゲが考えたよりもいっそう広範な哲学的な領域にまで拡張して,英国経験論との融合を図ろうというのが,「外部世界はいかにして知られうるか」のねらいなのである。このように,ほとんど同じ構造をもった論理学から出発して,フレーゲは最後まで実在論に忠実であったのに対して,ラッセルが実在論を全く放棄することなしに経験論へと傾斜していったことは興味ぶかいことである。しかし,「数学原理」が最後まである種の統制原理として働き,それから著しく逸脱することがなかったというのが,この書物をも含めてラッセル哲学の大きな特徴である。また論理学によってカバーできないところまで哲学的な問題を深追いしたいということもラッセル哲学だけでなく,英米哲学をドイツ哲学と区別する一つの要因であろう。このことは,「外部世界はいかにして知られうるか」における中性一元論の取り扱いからも伺い知ることができよう。中性一元論をとるか,ブレンターノ説をとるかということは,倫理学の網にかからないことなのである。
4
「外部世界はいかにして知られうるか」は,前書きと八つの章からなっている。最近の傾向と題する第一章では,この書物執筆当時のヨーロッパの哲学を,古典伝統派の哲学と進化主義,さらに論理分析の哲学というように三つに大別して,それぞれの特徴を論じている。古典伝統派の哲学とは,この当時英国でまだ余喘(ぜん)を保っていたブラッドリーなどに代表される英国化されたドイツ観念論のことであって,分析よりも総合を重んじるこのような哲学の難点が鋭く批判される。へーゲルを頂点とするドイツ観念論の哲学が,フレーゲ以来の近代論理学と調和しないことは,いまでは当然のことであるが,このことをはっきり主張したのはラッセルが最初ではないかと思われる。
進化主義の哲学とは,これに対してその当時名声をほしいままにしていたベルクソンや二一チェの哲学をさしている。ところが,進化主義の哲学はドイツ観念論以上に近代論理学の精神と合致しないのである。そして,当然のことながら,ラッセルの批判の的となる。ラッセルによると進化主義の哲学は,進化論の性急な一般化であって,哲学に期待できないようなことを哲学にさせようという乱暴な哲学であるということになる。これら二つの傾向に対して,ラッセルが自らの方法であるとして提唱するのが,論理分析を道具とする新しい哲学であって,その史上初めての解説がこの書物なのである。前書きでも述べられていることであるが,論理分析という方法が力強く著者にせまってきて,論理学のもついってみれば内在的な力に駆られて,この書物の哲学がいわば自動的にできあがってしまったという感じさえする。論理的な順序からいえば,哲学が論理学に先行すべきであろうが,ラッセルの場合はいうまでもなく,同じ論理分析を方法として採用している論理実証主義の哲学においても,論理学が逆に哲学を規制しているということは外から見ると一見奇異な感じを与えるかもしれない。しかし,論理学といってもラッセルの場合には「数学原理」の論理学にほかならないが,この論理学が,古典数学をすべて含む極めて実在論的な存在論であることを思い出すならば,こういった手法を採用するということは,少くともラッセルの場合には,プラトン的な意味で現実に存在している古典数学や論理学のなかにインスピレーションを感じとるということであって,むしろ西洋哲学の伝統に忠実な態度であるといえよう。ラッセル哲学が何かもの珍しい新しい哲学であるかのようにいう人もいるが,このように考えるとラッセル哲学のみならず,その後継者である論理実証主義なども,西洋哲学の伝統に対する反逆者なのではなく,むしろ,その正当的継承者であることがわかる。
第二章は哲学の基本としての論理学と題されているが,「数学原理」で一応絶頂に達した新しい論理学の手短かな紹介である。六十年も前に書かれているために,この章における近代論理学の紹介は必ずしも目新しいというわけではないが,一部専門家の間でしか知られていなかった新しい論理学を,古い論理学と対比させつつより幅の広い読者層に提供したという意味では興味ぶかい読みものであろう。とくに,近代論理学の哲学に対する関連を述べている箇所は,いまでも古さを感じさせない。
第三章はこの書物と同じ題名,「外部世界はいかにして知られうるか」と題されている章であって,ある意味でこの書物の基本的な主張が圧縮された形で述べられている。すなわち,のちに構成主義とよばれ,論理実証主義の初期においてカルナップによってくわしく検討されることとなった立場が哲学史上初めてまとまった形をとっているのである。
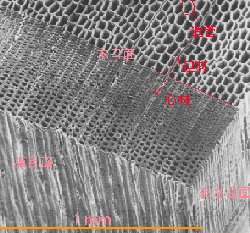 ラッセルはまずヒューム的な経験論者として登場する。すると,当然のことであるが直接与えられた経験,すなわち,感覚に与えられたデータ,つまり,感覚データのみが問題なく信用できるデータであるということになる。そして,疑っても疑いきれない感覚データをいわばかたいデータとして,それから他のあらゆる対象をやわらかいデータとして構成するという仕事にとりかかる。たとえば,私の目の前に見える机はかたいデータではなく,机のいろいろの外観から論理的に構成される論理的なフィクションである。ところが,'外観'は感覚に直接与えられる感覚データで,かたいデータの一種である。しかしながら,こういった構成にさいして,たとえば,机の形といった普遍者と,その形をした個々の外観という個別者が現われてくるのであるが,こういった二つの存在者は,いずれも直接一挙に把握することができるといういわゆる熟知の理論がここで伏線としてあらわれてくる。この理論はアウグスティヌスに発するといわれているが,この書物を,頂点としてラッセル哲学においては,やがて背景に消えていく理論である。さらに,感覚データと,それを指向する感覚作用を区別するブレンターノの説を初版では採用していたが,第二版(松下注:第2版は1926年に出版されている)ではそれを捨てて,その区別を認めないというアメリカの実在論者が提唱した中性一元論がとり上げられているが,すでに述べたように,いずれの説を採用しても,構成される外部世界の論理的構造には変りがない。
ラッセルはまずヒューム的な経験論者として登場する。すると,当然のことであるが直接与えられた経験,すなわち,感覚に与えられたデータ,つまり,感覚データのみが問題なく信用できるデータであるということになる。そして,疑っても疑いきれない感覚データをいわばかたいデータとして,それから他のあらゆる対象をやわらかいデータとして構成するという仕事にとりかかる。たとえば,私の目の前に見える机はかたいデータではなく,机のいろいろの外観から論理的に構成される論理的なフィクションである。ところが,'外観'は感覚に直接与えられる感覚データで,かたいデータの一種である。しかしながら,こういった構成にさいして,たとえば,机の形といった普遍者と,その形をした個々の外観という個別者が現われてくるのであるが,こういった二つの存在者は,いずれも直接一挙に把握することができるといういわゆる熟知の理論がここで伏線としてあらわれてくる。この理論はアウグスティヌスに発するといわれているが,この書物を,頂点としてラッセル哲学においては,やがて背景に消えていく理論である。さらに,感覚データと,それを指向する感覚作用を区別するブレンターノの説を初版では採用していたが,第二版(松下注:第2版は1926年に出版されている)ではそれを捨てて,その区別を認めないというアメリカの実在論者が提唱した中性一元論がとり上げられているが,すでに述べたように,いずれの説を採用しても,構成される外部世界の論理的構造には変りがない。
要するに,かたいデータである感覚データから出発して,この机,この本などといった比較的単純な対象からはじめて,遂次,外部世界を構成していくというのが,この章の目的である。しかし,この書物ではその概略がスケッチされているにすぎない。
さて「数学原理」のことばでいうと,階型(タイプ)が高くなればなるほどそれに対応する述語や関係は論理的フィクションとしての性格が強くなって,かたさをしだいに減じていくことになる。このように,データをかたいデータとやわらかいデータに二分し,本当の意味における存在者はかたいデータである感覚データに限られるが,それから論理的に構成されるやわらかいデータをもある程度存在者として認めようという姿勢は,経験論と論理学の融合として,極端ないい方が許されるとするならば,哲学史上画期的な試みである。フレーゲやそれを受けついでいるショルツにおいては,いわばドイツ的に,かたいデータとやわらかいデータの区別を問題にせず,数とか関数といったかなり抽象的な存在者にまで存在者として一人前の資格が与えられるのであるが,ラッセルの場合には,英国経験論の伝統により忠実である。しかし,こと論理学に関してはほとんど同じであるといってよい。なるほど,フレーゲの「算術の基本法則」とラッセルの「数学原理」は決して同じではないが,古典数学の論理的再構成を目指しているという点では全く同様な企てであるといってよい。実際,フレーゲやショルツは古典数学を,より存在論的,つまり,実在論的に,一方ラッセルは同じ古典数学をより経験論的に再構成しようという違いがあるにすぎないのである。このことは,同様なことを,ラッセルよりさらに経験論よりで,「世界の論理的構築」で企てたカルナップについてもいえることであろう。
こういうわけで,ラッセルがこの書物で企てたことを,英国経験論の単なる繰り返しであるとみなすことが誤りであると同時に,この書物は実在論で塗りかためられた「数学の原理」の単なる延長でもないのである。月並な言葉ではあるが,「外部世界はいかにして知られうるか」は,経験論と論理学,つまり,経験論と合理論という西洋哲学における二大潮流の統合という英雄的な企てをはじめて試みたいわば実験なのである。そして,この企ては後に論理実証主義論に継承されて現在にいたっているのである。
第四章は,物理学の世界と感覚の世界という標題で,かたいデータである事象から点や瞬間を構成する方法が説かれている。事象という概念は,ラッセル哲学だけでなく,ホワイトヘッドの哲学においても大きな役割りを演じているが,この書物においてはっきりと説明されているわけではない。しかし,個々の事象,すなわち,できごとが,この事象,あの事象というように特定される個別者であって,その間に時間的な前後関係と空間的な包摂関係が直接与えられる,すなわち,熟知される関係として与えられているものと仮定されている。こういった事象がどれくらい存在するかということについては十分明らかではないが,わたくしたちが感覚できないほど多くの事象が存在するということは認められている。たとえば,次第に小さくなっていく事象の系列を考えてみると,そのなかにいくらでも小さな事象が見出されることになる。限りなく小さくなっていく事象の系列を認めることは,経験論の立場からいうと極めて不自然であるが,ここで再びラッセルの実在論が前面にあらわれてくる。そして,こういった不自然な要請も,実は,「数学原理」からのやむを得ない要求であることが判明する。この章で述べられている時間空間の構成方法は,ホワイトヘッドによるものとされているが,デデキントやカントールによる有理数から実数を構成する手続きともたいへんよく似ている。いずれにせよ,この理論によって感覚の世界と物理学の世界が結びつけられ,物理学における点や瞬間の論理的構築としての性格が明らかになる。つまり,古典数学や古典物理学が正当化されるのである。
第五章は連続の理論と題されていて,主として連続の理論を歴史的に展望している。そして,第四章で展開された感覚データからの点や瞬間の構成が歴史的観点から再検討されている。
第六章と第七章は,それぞれ,歴史的に見た無限の問題と積極的無限論と題されているが,まず第七章で,有名なアキレスと亀の話しのような無限にまつわる間題が,集合論,つまり,無限論を認めれば難なく解決されるということが説かれる。これに対して,第七章はカントールによってはじめられた近代的集合論とそれと平行して展開されるフレーゲの算術の解説である。しかしながら,ラッセルがここで展開している集合論が極めて実在論的な集合論であるということは忘れてはならない。つまり,集合とは完結した全体であって,生成のプロセスのことではないという思想が,多くの場合,はじめから仮定されているのである。そして,「数学原理」の,また「外部世界はいかにして知られうるか」の背後にこのような実在論が控えていることは,事象の無限系列などに関連してすでに指摘したことでもある。実際,第四章で取り扱われた事象の集合は,予め存在する完結した無限集合で,この集合のこういった実在論的性格を見抜かない限り,第四章における点や瞬間の構成を哲学的に理解することは無理であろう。
最後に,第八章は,原因の概念とその自由意志の問題への応用,と題され,因果律の問題が実在論的な立場から論ぜられている。そして,われわれの自由意志も実は実在論的な外部世界の一部であるというあまり魅力のない結論に達している。
5
以上まとめると次のようになろう。この書物,すなわち,「外部世界はいかにして知られうるか」は,感覚データから出発して,外部世界を説明しようとするかぎり,経験論に忠実であるが,実在論的にしか解釈できない「数学原理」を道具としているために,感覚されない感覚データや事象の存在をも認めるという実在論への譲歩が行なわれる。というよりは,古典数学が完全になりたつライプニッツ的な世界の存在を予め仮定した上で,そこへ経験に与えられる感覚データの集合がはめこまれているのが,「外部世界はいかにして知られうるか」におけるラッセル哲学の構造なのである。そして,すでに述べたことであるが,この構造,すなわち,経験論を実在論のわく組みのなかで展開するという構造は,その後のラッセル哲学を事実上決定することになる。さらに,この構造が,「数学の原理」にはじまり,「数学原理」で絶頂に達するラッセルの論理学によって強く規制されていることも,すでに指摘したように否定できない事実である。つまり,ラッセルは論理をまずつくっておいてそれにあわせて哲学をつくった哲学者であるともいえよう。ラッセルやウィトゲンシュタイン,あるいは,フレーゲの哲学のことを論理主義の哲学と呼ぶこともあるが,無理もないことである。もっとも,論理主義とはこのような意味ではなく,数学がすべて論理学に還元できるという主張であって,論理学を重視する哲学のことではない。そして,この論理学の背後にある存在論のなかに,時間空間を構成するために必要な空間の包摂関係,時間の前後関係だけでなく,ラッセル自身はこれについてほとんど述べていないが,古典力学を成立させるのに要請されるいくつかの仮定ももり込まれている。(この辺の事情については,「人間の知識」を参照されたい。) こういった要請は,狭い意味における論理学で証明される主張ではないが,「数学原理」における無限の公理が古典数学を成立させるための要請として導入されたように,古典物理学を成立させるために要請されるのである。
こういうわけで,「外部世界はいかにして知られうるか」は,あるがままの古典数学と古典力学にまで経験論を実在論的に補完することによって得られた体系であるといえよう。こういった試みは,古典数学や古典力学をそのままの姿で認めるという意味で保守的であるが,同時に,プラトン以来の西洋哲学の正統的継承者となっているという事情をも見落してはなるまい。すでに強調したことであるが,この書物は西洋哲学における異端の書ではなく,むしろもっともオーソドックスな線上にある企てなのである。
しかしながら,現在でもこの書物で追求された方向に科学哲学が進んでいるかというと,事態はそれほど簡単ではない。ラッセル自らの「心の分析」,「物質の分析」,カルナップの「世界の論理的構築」などで同じ傾向の試みが続けられたが,一九三〇年代にはいると,カルナップをはじめとする論理実証主義者はこの方向を断念し,いわゆる物理主義に転じ,ラッセル自身も「意味と真実性の探求」などでこの転向に同調しているように思われる。しかし,この辺の詳しい分析は別の機会に譲りたい。