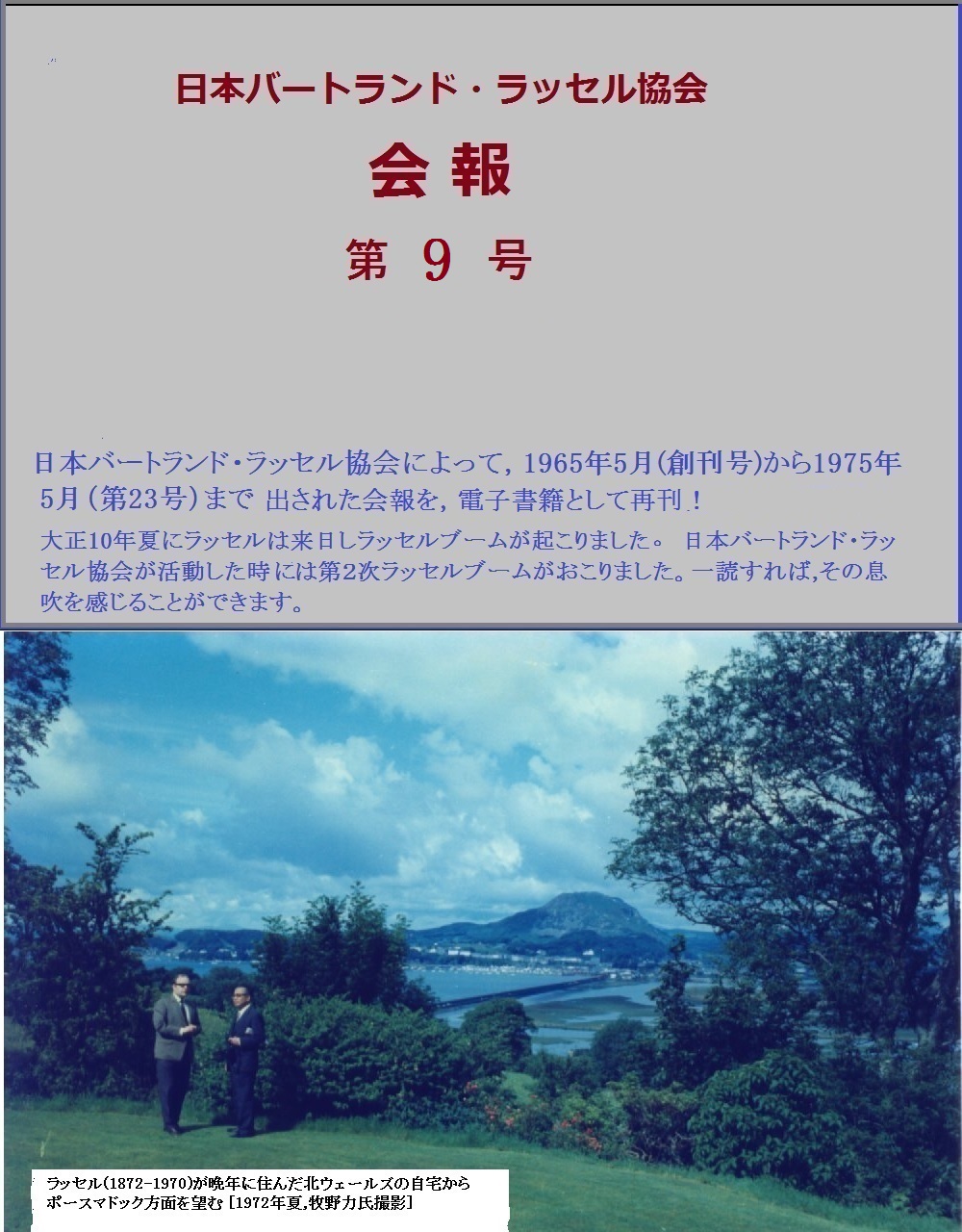著書解題8_ バートランド・ラッセル『西洋哲学史』(碧海純一)
*『日本バートランド・ラッセル協会会報』第9号(1969年2月)pp.4-5.
* 筆者の碧海純一は当時,東大法学部教授,ラッセル協会常任理事

楽天で購入する!
|
(ラッセルの)『西洋哲学史』(1945年)は,私の手元にあるアレン・アンド・アンウィン社の初版本で916ページに及ぶ浩翰な大著である。本書の価値については,実にさまざまな意見があるが,本書は,ラッセルの数多い著作の中でも出色のもののひとつであるにとどまらず,西洋哲学史の概説書としても全くユニークな,傑出したものだと私は信ずる。
本書が出版されたのは第二次大戦後のことであるが,その執筆は,主として,第二次大戦中ラッセルがアメリカに滞在していたときに行われたものと考えられる。のちに,「バートランド・ラッセル事件」として有名になった訴訟事件(1941年にラッセルが,ニューヨーク市立大学教授に任命されるはずだったのを結局阻止することとなった事件)のために,戦争中異郷で職を失ったかれに哲学史の講義を委嘱してきたのは,アルバート・バーンズ博士という風変りな金持の主宰するバーンズ財団であった。このためにラッセルは,一年半ほどをペンシルヴェーニア州で過すことになるが,この期間における講義の準備が,のちの西洋哲学史の執筆に大きく寄与したものと思われる。
人も知るとおり,ラッセルという人物は,フランシス・べーコン(1561-1626),ジョン・ロック(1632-1704),デイヴィッド・ヒューム(1711-1886),ジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)と続いてきたイギリス経験論の伝統を継承し,それに新たな発展を与え,現代の経験主義哲学の礎石を据えた功労者である。現代の経験主義哲学者は,しばしばその論敵から,「歴史的・思想史的パースペクティヴを欠いている」として批判されるが,ラッセルの『西洋哲学史』は,経験主義者の手で書かれた哲学史としても類を見ない存在というべきであろう。
このことは,何よりも,ギリシャ以来現代にいたる歴代の哲学思想の解釈・評価において,はっきりあらわれている。ソフィストや原子論者(特にデモクリトス)に対する高い評価,プラトンに対する痛烈な批判など,ギリシャ時代だけを例にとってみても,わが国の旧制高校などでわれわれが教えこまれた哲学史の既成像からは,およそかけはなれたものの見かたが,本書では随処に散見される。また,ドイツ観念論,なかんづくへーゲル哲学に対する仮借ない攻撃も,本書の著しい特徴である。古代においてはプラトンが,近代においてはへーゲルが,それぞれ最大の哲人であった,と教えられてきた戦前派・戦中派の日本人にとっては,とまどうようなことばかり書いてある。
本書における解釈・評価の独自性は,いうまでもなく,長所であると同時に,欠点でもある。本書だけで哲学史を学ぶことは,その意味でやや危険だということを記しておこう。何といっても,ひとりの人間が比較的かぎられた期間に,二千数百年に及ぶ西洋哲学の全歴史を書いたのだから,部分的にややできの悪い章や,読者に誤った印象を与えるようなパッセージがときおり見られることも否定できない。これは,ラッセルの非凡な学殖と筆力を以てしても,及びえぬところであろう。特に,カントに関する叙述は,この碩学に対して必ずしもフェアでない,という人もある。
このような欠点はあっても,この『西洋哲学史』は,第一級の哲学者自身の筆になるほとんど唯一の哲学書として,類書の中でぬきんでた地位をおそらく将来も永く維持しつづけるであろう。ひとたび本書をひもといて読みはじめると,およそ哲学に興味をもつ読者ならば,誰しもその魅力のとりことなって,時の経つのを忘れるであろう。その魅力の第1の要素は,ラッセルのトレード・マークである,例の明快・暢達でしかもウィッティな文体であろう。歴代の哲学者に対するかれの叙述や評価に賛成しない人でも,およそ英語を解するかぎり,この点では著者に脱帽せざるをえないはずである。文体の美しさは,どんな名人が訳しても,訳文では十分に再現できないが,ここでは,ラッセル一流の人を食ったものの言い方の一例をあげておこう。はじめはリヒァルト・ヴァーグナーの讃美者だった二ーチェが,あとでヴァーグナーと喧嘩をしたことについて,ラッセルはこう書いている。
この喧嘩ののち,ニーチェはヴァーグナーを手ひどく批判し,かれをユダヤ人であるとして非難したほどであった。しかし,ニーチェの一般的なものの見かたは,依然として(二ーベルンゲンの)『指環』におけるヴァーグナーのものの見かたに似たものであり,ニーチェの超人はジークフリートに酷似していた-ただし超人はギリシャ語を知っている点でジークフリートとちがっていたが。このことは奇異の感を与えるが,それは私の責任ではない。
これなどは,ほんの一例で,こうしたウィッティな箇所は全巻にばらまかれていて,読者をたのしませてくれるのである。哲学史は文学作品ではないから,文体やウィットだけでその価値がきまるわけではない。しかし,ラッセルのばあいには,一再ならず,ウィッティな寸言の中に,非凡な洞察が盛られているのである。
たとえば,アリストテレスについて,かれは言う。「アリストテレスの形而上学は,大まかに言えば,プラトンを常識でうすめたものといってよい。アリストテレスがむずかしいのは,プラトンと常識とは容易にまざらないからである。」これなどはアリストテレスの思想の特色を心にくいまでに巧妙に表現した警句であろう。たとえば,プラトンにおけるイデア論とアリストテレスにおける形相の理論とを比較してみるとき,私はラッセルのこの名言をつい思い出してしまう。何となれば,前者が,常識を徹底的に超越しているために,かえってわかりやすいのに対し,後者は,なまじ常識を顧慮しているがゆえに,晦渋難解なものとなっているからである。
本書の第2の魅力は,哲学ないし学問一般に対するラッセルの求道者的ともいうべき,きびしい態度が全巻を貰いているところにある。ラッセルによれば,学問の,そしてなかんずく哲学の本領は,かれのいう意味での「知的廉直」にある。それは,一切の希望的観測や自己欺瞞を排して,真理をあるがままに追求するひたむきな態度である。この角度から見ると,全く無私な,とらわれない眼光をもって世界の謎を解こうとしたBC5世紀以前のギリシャ哲学は,ラッセルにとって,哲学のあるべき姿のモデルとして満腔の賞讃の対象となる。かれによれば,原子論者デモクリトスこそ「……それ以後の古代および中世思想を毒したひとつの欠点を免かれた最後のギリシャ哲学者」であった。デモクリトス以前の哲学者たちの態度は「真に科学的」であったばかりでなく,「想像力と活力に充ち,冒漬のよろこびに溢れていた。」「かれらはあらゆるものに興味を示した-流星や日月食に,魚や旋風に,宗教や道徳に。かれらは透徹した知性と小児のような熱狂とを兼備していたのである。」そして,このような見地から,デモクリトス以後の哲学において「不当に人間に重点をおいた」ものの見かたが出てくることにラッセルは抗議するのである。特に,プラトン以後の伝統において道徳的教化への強い関心が「世界の学問的認識」への無私の努力を鈍らせる結果となったことを,かれは慨嘆しているが,このことは,ラッセル自身の哲学観を反映するものとして,私には大変興味ふかく思われる。
われわれがむかし教えられた哲学史では,ソクラテス以前のギリシャ哲学は,「単なる,素朴な自然哲学」にすぎず,ソクラテスにおいてはじめて人間中心の「真の」哲学がはじまり,それを一層発展せしめたのがプラトンであり,アリストテレスである,ということになっていた。ラッセルの評価は,このオーソドックスな見かたと正面から対立する。どちらが正しいかは,まさに論者の哲学観に依存する問題であるが,オーソドックスな教育を受けた日本の知識人にとっては,ラッセルのような立場をも一応理解しておくことが,視野をひろげる意味で,好ましいことだと私は思う。
本書の魅力・長所は,決して上述の2点につきるものではない。ことにギリシャを中心とした古代哲学に関する第1篇(約320ぺージで,全休の1/3強にあたる)は,最も生彩にとむ部分で,ここだけでも通読する価値は十分にある。本書の副題には,西洋哲学と「政治的・社会的背景との関連」において叙述するという趣旨がのべられているが,このふれこみも,古代の部分については,相当の実を挙げているとみてよいであろう。
名著とは一般にそういうものであるが,特にこの『西洋哲学史』は,できれば原文で読んでほしいと思う。その努力は必ずむくいられるはずである。そうはいっても,英語で読むのはどうもという向きには,幸いに市井三郎教授による名訳が,みすず書房から出ている。これは,私が読んだかぎり,第一級の,きわめて良心的な訳であり,安心して読者にすすめることのできるものである。(了)