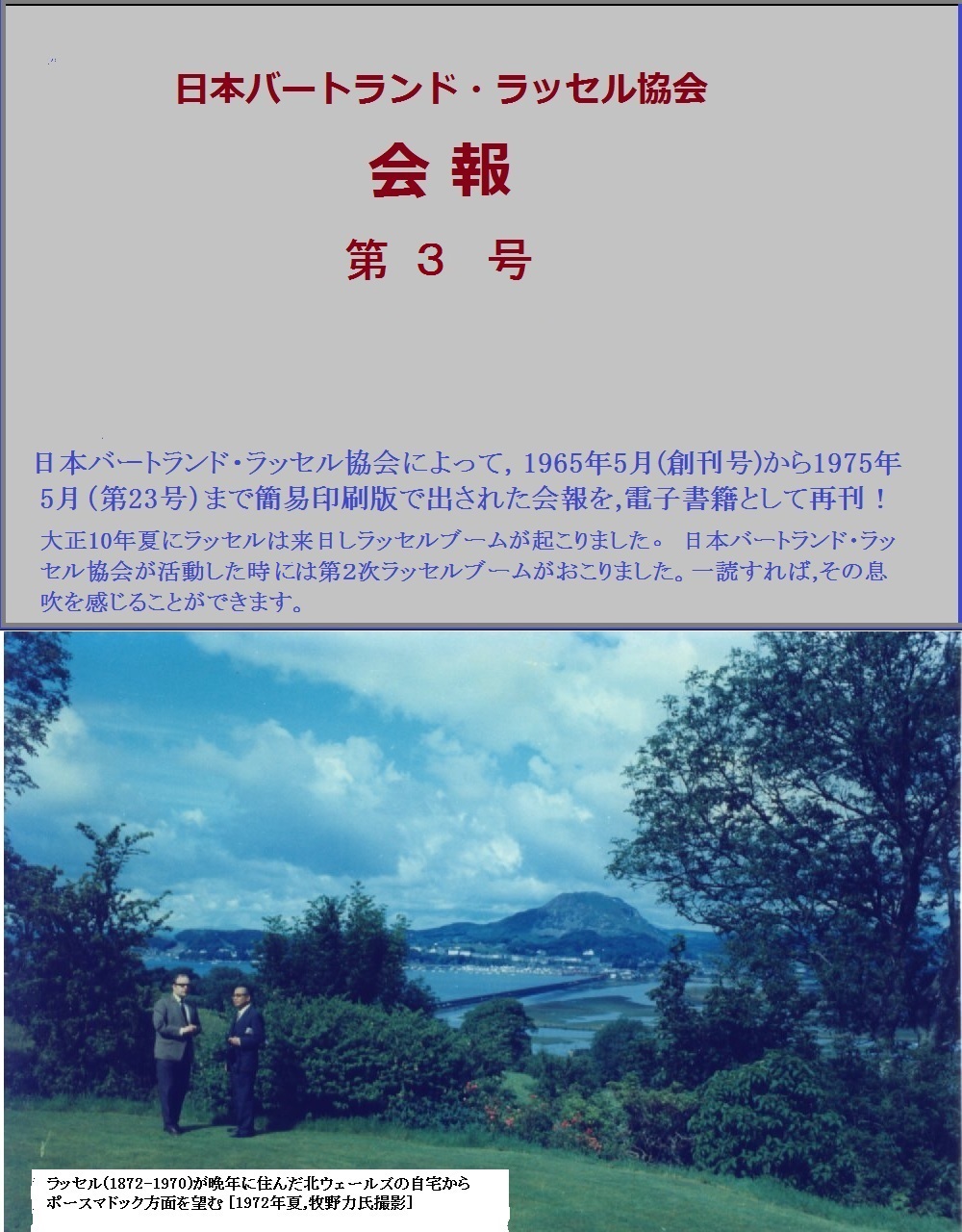
ラッセル協会会報_第3号
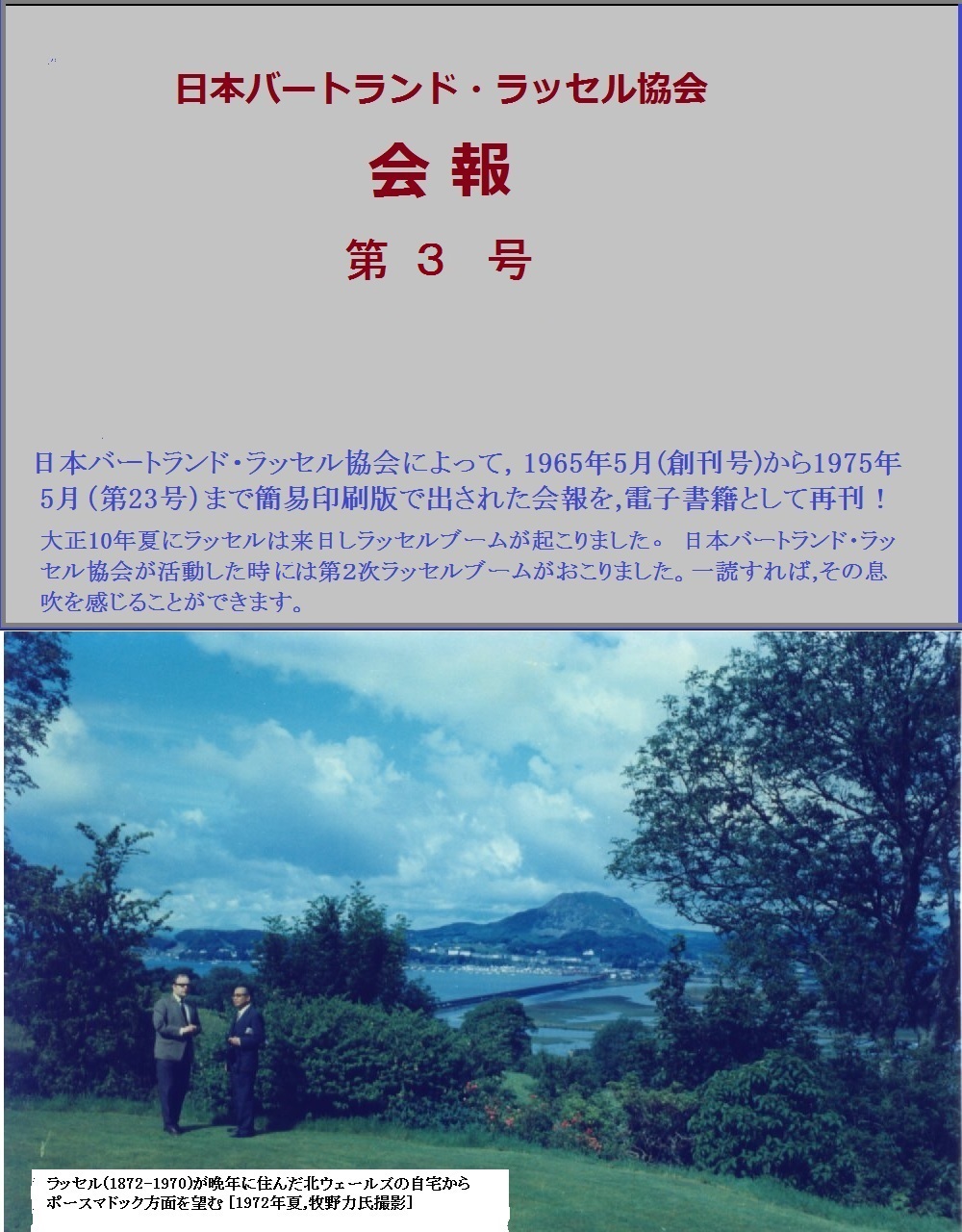 ラッセル協会会報_第3号 |
「今日,19世紀中葉まであらゆる思想の分野に対して,宗教が首を絞めあげていた実状を想像することは困難である。今では,大抵の国々で宗教はひどく守勢であり,'度量が大きく',鄭重で,つつましいから,ダーウィンがあらゆる教会の説教壇から攻撃され,へーゲルが異端者として公然と非難された時代に,われわれの頭を振り向けることは殆んど不可能である。合衆国のバイブル地帯や,アイルランドやスペインでの同様な行為が,今は最も敬虔な教会の信者たちからさえも苦笑され,慨嘆されている有様である・・・。」大げさに言えば,一世紀近くも前に生れたバートランド・ラッセル(1872年生)が,このような歴史的事実を,深刻に,子供心に感じながら,J.S.ミルの考えなどにヒントを得て,神の存在に懐疑の念を持ちながら,成長したのだということを,われわれは,まず,留意しておく必要があろう。引用されたゴーラの一節に似た感想を,ラッセル自身も「トマス・ペイン」の稿で述べているが,それはやがて本論で取りあげることになろう。
「18歳のある日,わたしはジョン・ステユワート・ミルの自叙伝を読んだのです。ところが,そのなかで,わたしは次の一文章を発見しました,『わたしの父は,「誰がわたしを造ったか」という問題は,答えられないということをわたしに教えた。なぜならば,その問題は,たちどころに,「誰が神を造ったか」という,もう一つの問題を暗示するからである。』その極めて簡単な文章が,今もそう思うのですが,第一原因による証明法の誤謬をわたしに明示したのであります。もしあらゆるものが,原因を持たねばならないとするならば,そのときは神にも原因がなければなりません。もし原因なしに何かが存在することができるとするならば,神と同じように,世界であってもよいことになりましょう。そうなると,その議論には,何の妥当さもあり得ないことになります。それは,まったく例の印度人の意見と同じであります。それによりますと,世界は一匹の象の上にあり,その象は一匹の亀の上にあるというのです。ところで「亀はどうなんです」と聞かれたとき,その印度人は「話題を変えたらどんなものでしょう」と言ったということです」(p.12)皿 ラッセルの性格とキリスト
「わたしの考えでは,キリストの道徳的性格には一つの重大な欠点があります。それは彼が地獄を信じていたということです。真に深く人情味のある人ならば,永遠の罰というものを信じることは出来ないという気がいたします。福音書に描かれているキリストは,たしかに永遠の罰を信じていたし,彼の説教に耳を傾けようとしないひとびとに対する報復的な憤激の反復されているのを発見するのであります- これは説教者には珍しくない態度ではありますが,たしかに至高の立派さからは,多少,おちるのであります。たとえば,そのような態度は,ソクラテスには見られません。彼が自分の意見に耳を傾けようとしないひとびとに対しても,極めて愛想がよく,思いやりがあるのがわかります。そしてわたしの考えでは,憤慨の線にそうより,その線にそっていくことが聖人には,はるかに適わしいものであります・・・・・・。」IV 自由人の信仰
「福音書のなかで,キリストがこう言っているのを発見なさるでしょう。'なんじら蛇どもよ,さそりのともがらよ,いかにして地獄ののろいをのがるべけんや' それは彼の説教を好まなかったひとびとに向かって言われたのです。それは実際,わたしの考えでは,最善の語調とは言えません。もちろん,聖霊に対する罪については,よく知られているテクストがあります。'聖霊にさからいて語るものは,この世においても,来世においても許されざるべし。' そのテクストは世の中に,言いつくされないほどのみじめさを引き起こしました。と言うのは,種々雑多なひとびとが聖霊に対する罪を犯したと想像し,この世においても来世においても許されないだろうと考えたからです……。」
「いちじくについてどんなことが起ったかは,ご記憶のことと存じます。'彼(イエス)飢えたまう。路の傍なる一もとのいちじくの樹を見て,そのもとに至り給いしに,葉の外になにも見出さず。まだいちじくの季節にあらざればなり。これに向いて '今よりのち,いつまでも汝の果を食うものあらざるべし, と言いたまう……' そしてピーターが彼に言うには '主よ,汝ののろいし,いちじくのたちどころに枯るるを見たまえ'。' これは極めて奇妙な話であります。なぜならばそれはいちじくのみのる季節ではなかったのであって,樹をのろうことは実際出来ないからです。'……。」(『宗教は必要か』p.27)
「根本的には,宇宙における人間の立場についての,わたしの見解は今も同じである……しかし,もしわたしが今日書いているのだとしたら,多少,修正したいと思う2つの点がある。これらのうち第一は唯物論に関するものであって,第二は善悪の概念の範囲に関するものである・・・・・・。」この「自由人の信仰」は,ラッセルの宗教論のうちでは,珍らしく,詩的ですらあるほどに格調の高いものであって,彼の若い時代の一つの記念塔である。
「唯物論に関して言えば,このエッセイに表現された見解は大体において唯物主義的なものとみなされることであろう。しかし形而上学的に言えば,わたしは決して物質の実在を信じているのではない。わたしは,物質を日常の目的に便利な,物理法則の大体の記述として論理構成であるとみなしているに過ぎない。普通考えられているところでは,物質は持続し,力を及ぼすはずになっているが,相対性原理の物理学によれば,終局的に存在するのはすぎ行く出来事の世界であって,これはある法則によって共存し,相互に継続するのである。恒久的な物量というものがあるのではなく「力」と呼ばれるような実体があるのでもない。この理由からして,物質を持続するとみなすことは,個人的な精神が持続するとみなすのと同様,想像的な誤謬である・・・・・・。」
「わたしが,このエッセイを書いた当時,わたしは善とか悪とかが,いわゆる「客観的」なものであると信じていた。すなわち,あるひとが,あることを,その結果においてだけではなく,それ自身において,善だと判断し,その一方他のひとが,それ自身において悪だと判断したならば,二人のうちどちらかが間違っていなければならないと信じていたのである。今や,わたしは善と悪とは,いわゆる「主観的」なものであると信じている。しかしこのことの実際に及ぼす影響は,想像される程には違ってこない・・・・・・。」
「外部から見れば,人間の生命は,自然の力に比較したら小さなものである。奴隷は「時間」「宿命」「死」を礼拝するように運命づけられている。なぜなら,それらのものは,彼が自分自身のなかに見出すなによりも,もっと偉大であり,彼の思想のすべては,それらのものが滅ぼしてしまう代物だからである。しかし,それらのものが偉大であるとしてもそれらのものについての考え方が偉大であり,それらのものの非情の壮観を感ずるということは,もっと偉大である。そして,そのような思想は,われわれを自由人にさせるのである。われわれは,最早,必然の前に,東洋風の服従によって,頭を下げることをしないで,われわれはそれを吸収し,それをわれわれ自身の一部分にするのである。個人的な幸福のための努力を放棄し,一時的な欲望に対する熱意のすべてを追放し,永遠なものに対する情熱に燃えること- これが解放であり,自由人の信仰である。そしてこの解放は宿命について冥想することによって行われる。なぜならば,宿命そのものは,時の浄火によって清められねばならぬようなものを何も残さない精神によって征服されるからである。V 努力と諦観:トマス・ペイン
「あらゆるきずなのうちで最も強い,共通の宿命のきずなによって同胞と結合された自由人は,新しい視野が常に自分と共にあって,あらゆる日常の仕事に愛の光をそそぐことを発見する。人間の一生は夜を徹して長い路を行くようなもので,眼に見えない敵にとり巻かれ,疲労と苦悩に悩まされながら,少数のものしか到達できず,なにびとも長くそこにとどまることのできない目的地に向けて進むのである。ひとびとが進んで行くにつれ,ひとりずつ,われわれの同志は,全能の死の暗黙の命令にとらえられ,われわれの視野から消えて行く。われわれが同志を助けることのできるのは,ほんのつかの間で,そのあいだに,彼等の幸福か不幸はきまるのである。彼等の行くてに陽光をそそぎ,彼等の悲しみを,同情の慰めによって軽くし,不断の愛情の純粋な悦びを与え,衰える勇気を力づけ,絶望の時に信念をつぎ込むことがわれわれの生涯でありたいものである。
「人間の一生は短く,無力である。彼と,すべての人類のうえに,ゆるやかではあるが,確実な宿命が無慙に暗くおちてくる。善悪に盲目で,破壊には無頓着に,全能の物質は,その残酷な道を回転して行く。今日は最愛のものを失うように運命づけられ,明日はわが身も暗黒の扉を通らねばならない人間にとっては,いまだ打撃がふりかかって来ないうちに,彼の短い一生を高邁なものにするところの高雅な思想をいだき,宿命の奴隷の臆病な恐怖を潔しとしないで,自分の手で築いたところの殿堂で礼拝し,偶然性の帝国に恐れることなく,外部の世界を支配する気まぐれな専制から解放された精神を維持し,人間の知識と非難とを,しばらくの間,認容する不可抗力に誇らかに挑戦して,疲労はしているが,不屈のアトラスのように,非情の力の乱暴な行進にもかかわらず,彼自身の理想が築きあげた世界を独力で支えることが,これからの仕事として残っているのみである。」
「公共事業-1775年の彼の奴隷制度反対-に参加した当初から,彼の死亡の日まで,彼は徹頭徹尾,自分の政党と反対党とを問わず,あらゆる形式の残酷さに抗議した。当時イギリス政府は苛酷な寡頭政治であって,極貧階級の生活水準を低下させる手段として,議会を利用していた。ペインはこのいまわしさの唯一の改善策として,政治的な改革を提唱したが,そのため命からがら逃亡しなければならなかったのである。フランスにあっては,不必要な流血に反対したため,彼は投獄され,すんでのことで殺されるところであった。アメリカにおいては,奴隷制度に反対し,独立宣言の原則を支持したため,彼が政府の支持を最も必要とした時に,政府によって見離された。もし,彼が主張し,今日多くのひとびとが信じているように,真の宗教は「正義を行い,仁慈を愛し,同胞を幸福にすることである」ならば,彼の反対者たちのなかには,彼に劣らず宗教的なひととみなされる資格を持つものはひとりもなかったのである。……今日ではイギリス教会の大主教でもいだくような意見であった……圧迫された者たちへのこれらのチャンピオンたちのすべてにとって,彼は勇気,人間味,誠実の模範をかかげた。公共の問題がからまってくると彼は個人的な慎重さを忘れた。そのような場合の例にもれず,世界は彼が利己主義を持たなかったために,彼を罰したのである……」結び