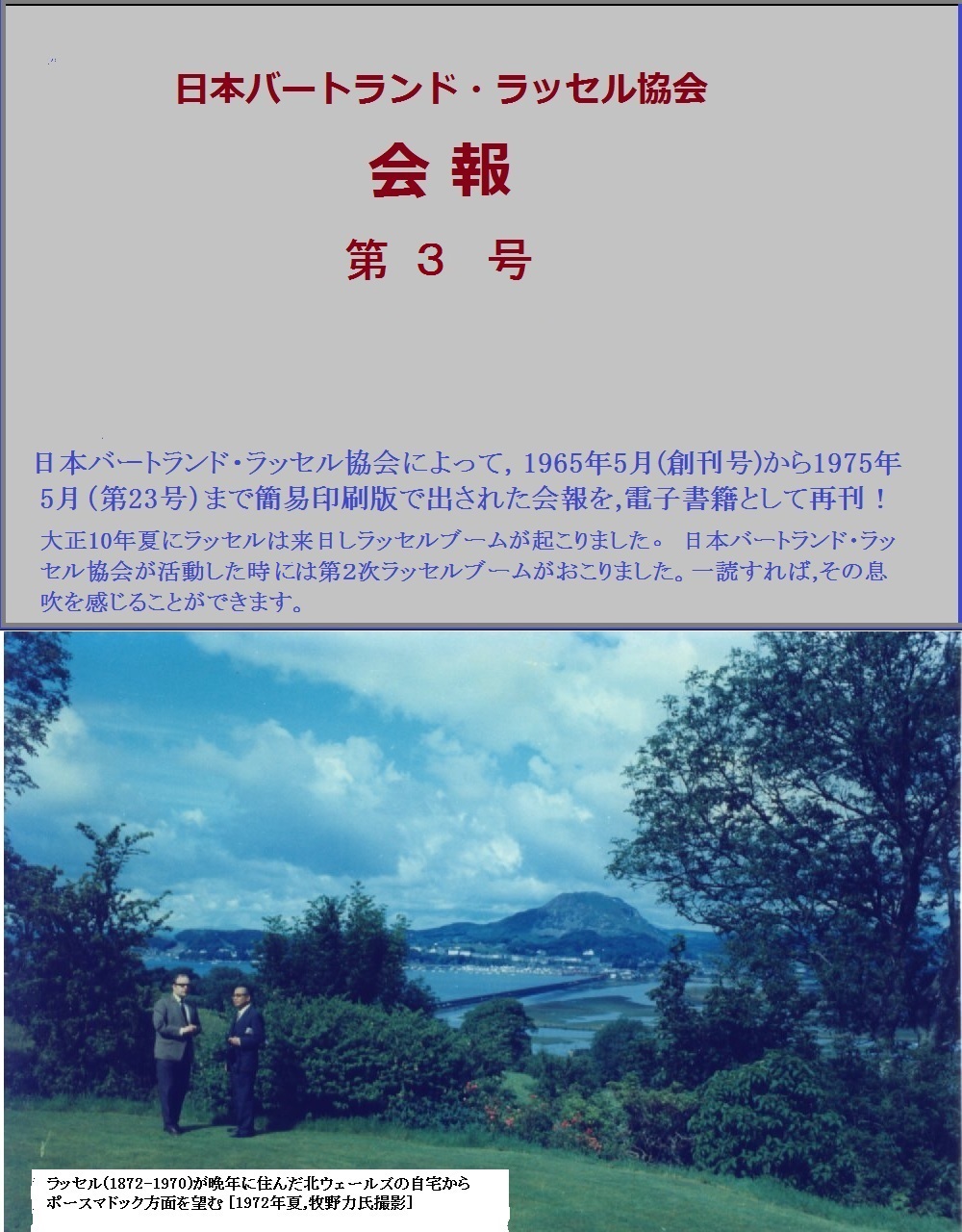
ラッセル協会会報_第3号
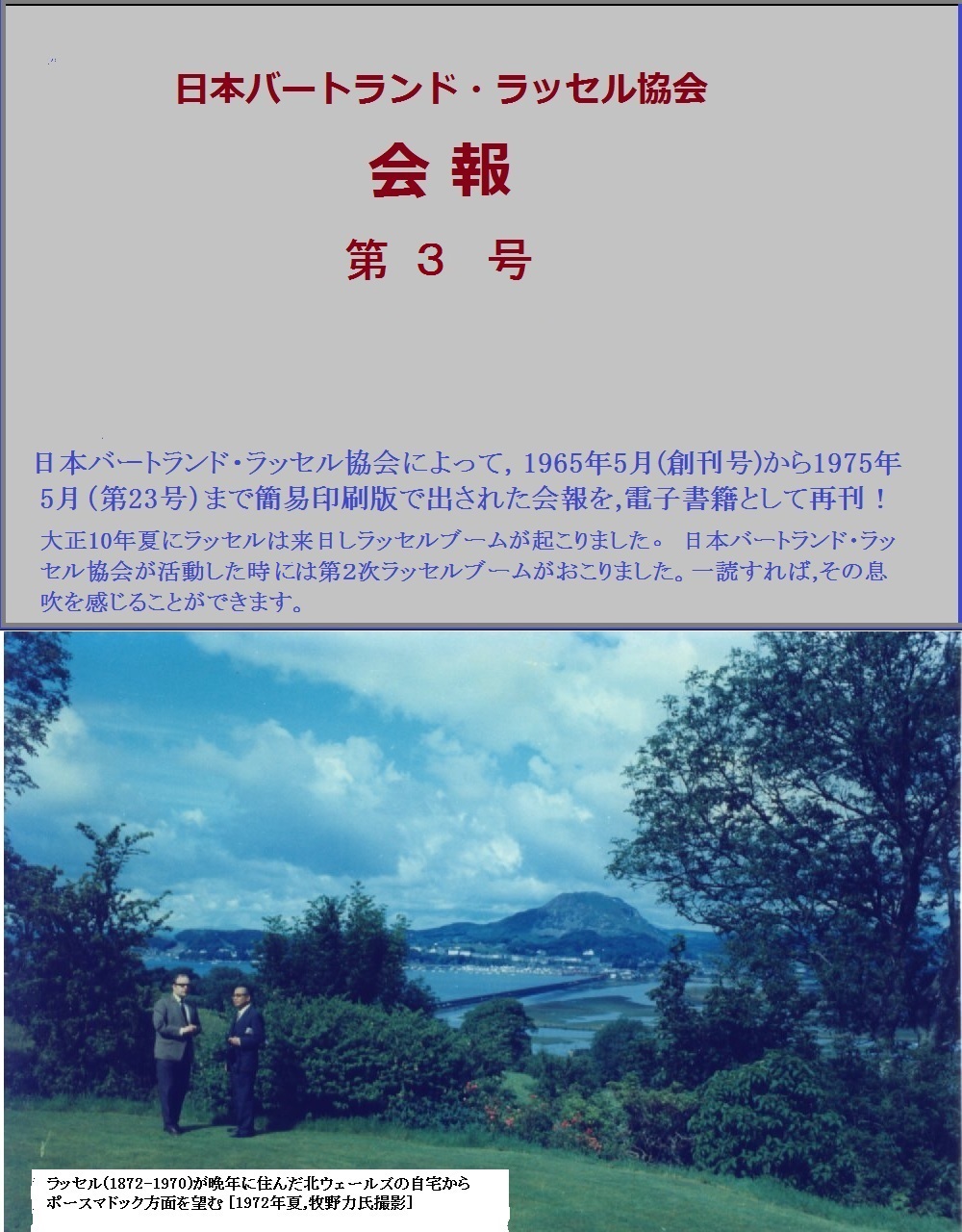 ラッセル協会会報_第3号 |
「たとえどのような欲望であれ,誰の欲望であろうと,わたしは欲望の満足それ自体を良きものと考える。しかしさまざまな欲望は,時には両立しうるが,両立しえない場合もある。もしAとBとが互いに結婚したいと欲すれば,両者ともに満足させることが可能である。だがもしおのおのが,自分は殺されずに相手を殺そうと欲すれば,少なくとも一人は失望しなければならなくなる。したがって結婚は殺人より良きものであり,愛は憎悪より良きものである」(1944年,シルプ編『B.ラッセルの哲学』中の「批判への答え」)>。ここで言われている「神」が,どのような特定宗教の神でもなく,スピノーザのいった「永遠の相下における神への知的な愛」に意味されているようなものであることに注意する必要がある。またかれはいう。「究極的価値は〔社会とか国家といった〕全体ではなくて,個人の中に求められねばならない。良き社会は,それを構成する各個人が良く生きるための手段であり,それ自体において独自の価値をもつものではない」(1949年,『権威と個人』)。
「正しい欲望とは,できるだけ多くの他の欲望と両立しうる欲望のことである」(1954年,『倫理と政治における人間社会』)。
「さまざまな人々における創造衝動は,本質的に〔相互に〕調和的である。……紛争を介在させてくるのは所有衝動である。…最良の生活とは,創造衝動が最大の役割を演じ,所有衝動が最少の役割しか演じない生活であり,最良の制度とは,可能なかぎり最大の創造性を産み出し,自己保存と両立しうる最低限の所有性しか産まない制度のことである。」(1916年,『社会改造の諸原理』)。
「生命力を助長するためには,単なる生命以外の何物かに価値をおくことが必要である。生命にのみ専念する生活は動物的であり…もし生活が十分に人間的となるためには,ある意味で人間的生命の外側にあると思われる目的,つまり非個人的で人類を超えた,神あるいは真理,美,といったなんらかの目的に奉仕しなければならない」(同書)。
「見事な数学的推理から与えられる美的な喜びは依然として存在する。しかしこの点においてもまた幻滅があった。・・・数学の基礎にひそむ矛盾の解決(ラッセルの「タイプの理論」のこと)は,真であるかも知れぬが美しくはない理論をとることによってのみ可能であると思われた。……数学において見出そうとずっと期待しつづけてきたすばらしい確実性は,どう抜け出したものか分らぬような迷路の中に失われた。(そのことは)もし私の禁欲的な精神状態が弱まりはじめたのでなかったなら,私を大いに悲しませたことであろう。……しかしその(禁欲的な)気分は去りはじめ,最後に第一次世界大戦によってまったく払拭された。……気分のこの変化において,あるものが失われた。……失われたものは,完全性と確定性と確実性とを見出そうとする希望であった。得られたものは,私の嫌いなある真理への,新たな服従であった。・・・私はもはや,知性が感覚よりすぐれているとか,プラトンのイデアの世界のみが『真実の』世界を知らしめる,などとは感じない。以前には,感覚や感覚の上にきずかれた思想を,一つの牢獄と考え(たが):…・いまでは(それを)牢獄の格子としてでなく,窓として考える。・・・そして物を歪めぬ鏡となることに,できるかぎりつとめることが,哲学者の義務であると考える。しかしまた,われわれの本性そのものからくる避けがたい歪曲をはっきり認めることもまた,(哲学者の)義務である。・・・有神論者が神に帰するようなひろい公平な見方に達することは,われわれには不可能であるが,それに向ってある距離を歩むことはわれわれにもできる。そしてこの目標への道案内をすることこそ,哲学者の最高の義務なのである」(1959年,『私の哲学の発展』)「それに向ってある距離を歩む」過程で,かれの理論哲学は内容の変化をとげていった。対象というものを感覚データにもとづく「論理的構築物」とみなす,という1910年代の結論は放棄されてゆき,感覚データのみから対象は構築できず,「準恒存の公準」とかれが呼んだものがつけ加わらなければならない-もっと平たくいえば,「動物的信念」が加わらねばならない-ということになった。(これはホワイトヘッドの立揚への接近である。)その他,因果性,原因,帰納,等々についてもかれの見解は変っていった。理性的な自己吟味によって,自説の誤まりを公けに認めること,しかもなおそこから「ある距離を歩む」努力を更新すること,ここにラッセル哲学の真骨頂があるといえよう。