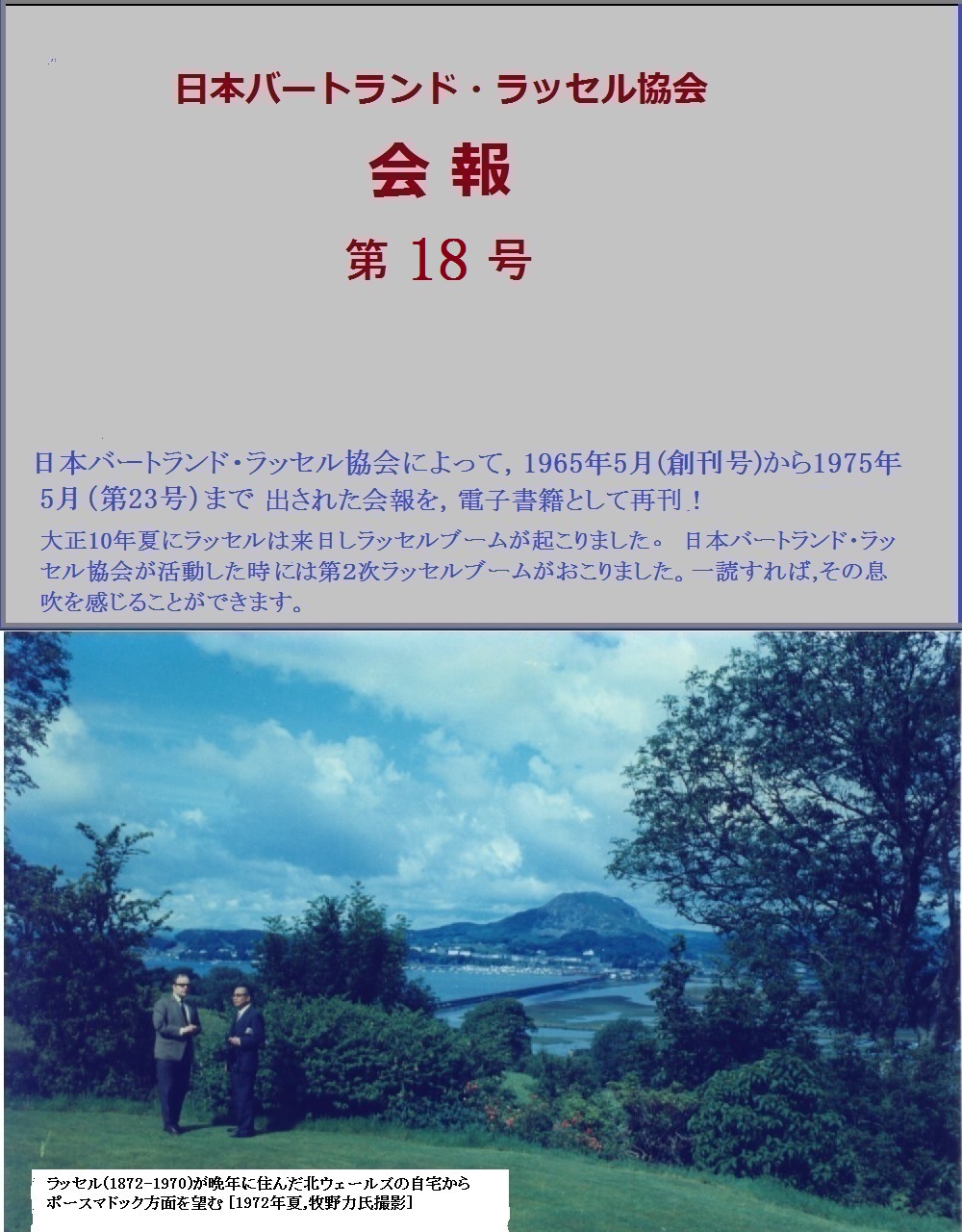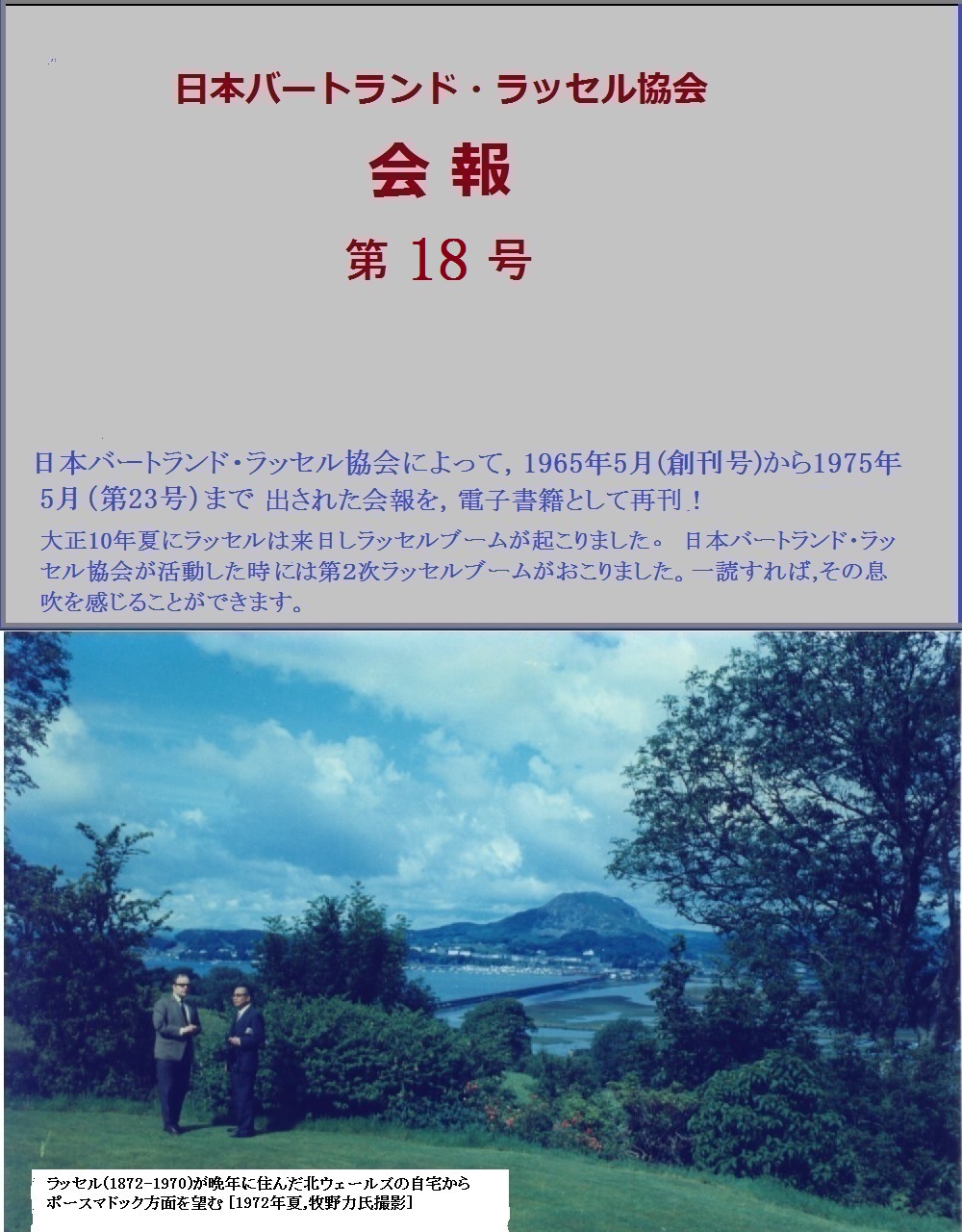東宮隆「バートランド・ラッセルの一面」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第18号(1971年6月)p.1
* 以下は、Russell Remembered, by Rupert Crawshay-Williams, Oxford U. P., c1970、から、私(=東宮)がおもしろく思った個所を拾い出したもの
* 東宮隆氏は、当時、東京工業大学教授、ラッセル協会理事
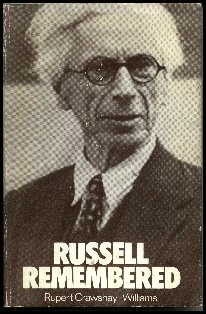
-ラッセルは、食事と就寝のときのほかは、いつもパイプをくゆらせていた。髪はながく、ふさふさとして、真白だった。背は決して高いほうではなかったが、身のこなしはしゃんとして、背の低さなど気にやむところは未塵もなかった。
-かれの会話の反応のしかたはまるで引きがねみたいに速かった。ひとの意見は、どんなものでも、じっと聴き入った。かれは微笑を絶やすことのない聞き上手だった。話相手は、そのため、何となく気がらくになるのだった。何しろ、はじめてラッセルと話をかわすことは、その人にとって、知的には、女王のとなりで食事をとらなければならないのと同じくらい気の重いことであったが、ラッセルは、高名な知識人のわりには、親しみやすい、気のおけない人であった。有名人も普通人と同じように知的な議論よりはゴシップや、天気の話のほうが好きなものだ、とラッセルはハッキリ言っていた。
-ラッセルが思想家として大きな影響を及ぼしたのは、何と言ってもかれが大量にものを書いたからではあるが、決してそれだけではなく、その書いたものが、気が利いていて、明快、簡明、論理的であり、人間味の溢れたものだったからである。だが、ラッセルの書いた2つの風刺小説については、世評は必らずしも良くなかった。スタイルはいかにも18世紀ふうだし、知的内容も流行おくれと言えないことはなかった。わずかに例外は -例外としては重要だが-、『オブザーヴァー紙』上のアンガス・ウィルスンがあっただけである。
-ラッセルの機智には、だいたい、何とはなしの誇張がある。これが時にラッセルの言葉をあらっぽく感じさせるのである。一例をあげると、デューイの真理の理論について、『西洋哲学史』はつぎのような述べかたをしている。「『朝食のとき、コーヒーをおのみになりましたか』と誰かにきかれたとすれば、普通の人なら、さあどうだったかな、と思い出そうとするだろうが、それがデューイの弟子だったら、『待ってください、実験を2つやってみなくては何とも言えません』と答えることであろう。」しかし、これは、デューイの理論を正しく解したものとは言えない。プラグマティズムの態度は、判断の検証とか確認にかかわるもので、判断のそもそもの形成を問題にするものではないからである。第一、プラグマティズムは、ラッセルの言葉に含まれている感じほど馬鹿げたものではない。しかし、ラッセルのほうは、この点を百も承知で、独特な言いかたをしているのである。ラッセルは「不公平」な議論が好きなのである。(松下注:「ラッセルは誇張するのが好き」というのはあたっているだろうが、「デューイの★弟子★なら」と言っていることから、偉大な人間の弟子は得てして不肖な人間が少なくない、といったニュアンスがあるかも知れない)
-ラッセルは伯爵という称号を使わなかったと一般に信ぜられている。伯爵を継いだのは1931年だが、ラッセルはすぐにはこれを使おうとしなかった。相変らず「バートランド・ラッセル」でものを書いていた。しかし、社交関係では、かれは次第に称号を使い出していたのである。若いときから生涯を通じてラッセルがひとのために投げ出した金銭は相当の額にのぼっているが、しかしラッセルは自分が社会主義者だから止むをえずそうしたとは感じていなかった。同じようにラッセルは、社会主義者だから伯爵の称号を使ってはならぬとは思っていなかった。世襲の称号など廃止すべきだというのがむしろかれの考えかたであった。貴族の大半は、「爵位はこんにち無意味だ」と言いながら、それによって、やましさをまぎらわせているのに、ラッセルは、どちらかと言えば、爵位をたのしんでいた。ホテルやレストランで、いざと言うとき、それは便利だったからである。(終)