市井三郎「バートランド・ラッセル」
* 出典:『社会科学大事典』v.18(鹿島出版会,1974年)pp.311-312.
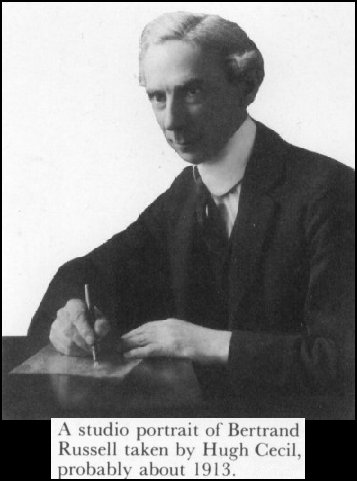 ラッセル(Bertrand Arthur William Russe11, 1872-1970)を一口に規定することは困難であるが,かれ自身がかつて自分を評したように、「逝ける時代(つまり西欧近代)の最後の生き残り」であるとともに、きたるべき新しい時代の先ぶれ(先駆者)でもあった,とでも評すべき哲学者であろう。
ラッセル(Bertrand Arthur William Russe11, 1872-1970)を一口に規定することは困難であるが,かれ自身がかつて自分を評したように、「逝ける時代(つまり西欧近代)の最後の生き残り」であるとともに、きたるべき新しい時代の先ぶれ(先駆者)でもあった,とでも評すべき哲学者であろう。
イギリス貴族(伯爵)の一員として生まれ,ケンブリッジ大学へはいるまでは,家庭教師(複数)による個人教育によって成長した。哲学と数学とを専攻した彼は、同大学を卒業した後にも,フェロー(寄宿研究生)としてケンブリッジで十数年をすごした。その間に彼は,
ラィプニッツの論理学思想(遺稿として百数十年うずもれていた思想)を解明したりしたが,そのことは新しい記号論理学の思想的境位に開眼することでもあった。だからケンブリッジ大学での師ホワイトヘッドとの協同研究がはじまり,あらゆる数学を記号論理学的に基礎づけようとする仕事に熱中し,1910年から数年にわたって『プリンキピア・マテマティカ』(Principia Mathematica,3 vols.)が共著としてうまれるにいたる。その間にもラッセルは,きわめて具体的な内外の政治問題にも,強烈な関心をいだき続けた。『ドイツ社会民主党論』(German Social Democracy) を処女作として刊行したのは,1896年であった。(右写真出典:R. Clark's Bertrand Russell and His Life, c.1981)
ラッセルにおける純粋な知的活動と社会的・政治的な実践活動とを区別するのはむつかしいが,それらふたつの関心・活動が融合してあらわれたものが,第一次大戦にさいしての反戦活動だといえるだろう。純粋な知的活動として1914年の『外界の認識』(Our Knowledge of the External World) があげられるとともに,数多くの反戦パンフレットの著述をあげねばならぬからである。1918年に彼は,この反戦言論のゆえに半年の投獄のうきめにあうが,すでにケンブリッジ大学からは追放されており,たんなる反戦をこえて、『社会改造の諸原理』(The Principles of Social Reconstruction, 1916) なる著書をも公刊していたのである。この投獄中に書いた『数理哲学入門』(Introduction to Mathematical Philosophy, 1919)は著名であるが,出獄後も彼は革命直後のソヴィエト・ロシアを訪れて批判的言辞をろうしたり,当時の中国に招かれて1年間講義(北京大学で)して『中国論』(The Problem of China, 1922)をものしたり,精力的な活動を続けた。純粋に知的な活動とは区別される全人間的な思想上の大転換は,1903年に書かれた『自由人の信仰』(The Free Man's Worship) に明らかにみてとることができる。(松下注:発表されたのは Independent Review, v.1(1903年12月号)であるが、執筆したのは1902年)
1920年代に彼は,イギリス労働党の候補として総選挙にも立つのだが落選し,幼児教育の実践に多大のエネルギーを注ぐにいたる。この実験学校の体験は約8年続くのだが(1935年まで),この時期はもっとも多方面にわたってラッセルの反逆的活動が旺盛をきわめており,『教育論』(On Education, 1926)だけではなく,『なぜわたしはキリスト教徒でないか』(Why Iam not a Christ1an?, 1927),『結婚と道徳』(Marriage and Mora1s, 1929),『なぜわたしは共産主義者でないか』(Why Iam not a Communist?, 1934)等々,かずかずの反俗的著作をものした。ヴィクトリア時代の社会的偽善への挑戦と,新しくきたりつつある時代への率直な懐疑とを,ともに表明したのである。だが社会的通念(アングロサクソンの)へ挑戦したむくいはてきめんにあらわれ,1940年にアメリカのニューヨーク市立大学へ哲学教授となる招きを受けながら,「非道徳」のかどで反対訴訟がおこされ,任命は取り消された。さる財団(注:バーンズ財団)の支援によって第二次大戦中,西洋哲学史の研究・著述のために滞米しえたが,大戦末期に母国イギリスのケンブリッジ大学へ招かれて帰国し,同校で講ずるにいたる(松下注:米国に渡ったのは家族を戦禍から守るためであり、西洋哲学史の執筆のためではない。)。その前後に,『意味と真理の探求』(An Inquiry into Meaning and Truth, 1940),『人間の知識』(Human Knowledge; its scope and limits, 1948)を公刊して,基礎的な認識論の問題で,伝統的イギリス経験論をのりこえる哲学的境地を表明するにいたる。
1950年は彼にとって,世俗的栄誉が積み重なった年であった。イギリスの文化勲章にあたるオーダー・オブ・メリットが授与され,さらにノーベル文学賞までが授与された年であった。だがラッセルの真骨頂は,それ以後の日々にあらわとなる。偽善化した社会通念へあくまで反逆を企てる姿勢は,旺盛であり続けた。1954年にかれは,死の直前のアインシュタインのよびかけに応じて,パグウォッシュ運動をはじめるのである。水爆の威力が人類の絶滅を結果しうることを知ったラッセルは,一切の核兵器廃棄運動を世界的に展開するにいたる。『人類は将来をもつか』(Has Man a Future?, 1961)という直載な表現の著述を公刊する一方,かれは率先して自国イギリスの国防省前にすわりこみデモを敢行し(1961年),「百人委員会」の名を全世界に知らせた。1965年には,アメリカのヴェトナム戦争に反対する運動を開始し,「ラッセル平和財団」の名のもとにアメリカ非難声明を公にした。そればかりではなく,アメリカのヴェトナムにおける戦争犯罪を裁くところの,民間法廷を開くことを主唱し,フランスの哲学者サルトルなどの協力を得て,現実にその国際法廷をひらきアメリカの有罪を宣告したのである。
前記の『外界の認識』は,理論的哲学者としてラッセルを不朽のものにした。というのはその著述によって,中欧ウィーンにおこった論理実証主義の運動に先鞭をつけただけではなく,いわゆる自由世界の哲学界を一変して分析哲学(第二次大戦後に)に向かわせるような威力を発揮したからである。その点では,同じケンブリッジ大学にいた哲学者ムーアや,オーストリア出身のユダヤ人でラッセルのもとに留学したウィトゲンシュタインらの影響力に,優先するといってもいい。だが記号論理学的分析を哲学に導入するというラッセルの独創性とともに,やはり前記の彼の著述『自由人の信仰』が示しているような,新しい価値理念の提唱 -科学や論理学によるだけでは規定しきれない分野での覚醒- に,彼の思想家としての独自性をみるべきであろう。『自由人の信仰』は,一切の伝統的宗教心情からはなれ,現代の科学的宇宙観から人間の連帯意識をみちびきだす提案であり,結果としてそれは,幅広い人間愛を説く哲学となったのである。この,理論的哲学 -あくまで狂信性を排して理性的熟慮がきりひらく地平に希望をもつ姿勢- と人間愛の実践哲学との統合に,彼は死にいたるまで忠実だったというべきだろう。純粋に知的な認識論においても,かれは伝統的な感覚主義的経験論だけでは科学的認識さえ基礎づけることができない,ということを悟り,超経験的な公準が必要であることを主張するにいたった。また完全な個別主義だけでは科学的世界像すら構築できない,ということを論証したりした。自らコミットした立場の欠陥をもこのように自認するという「知的誠実さ」は,彼の社会的実践運動にも一貫している。自己が生まれ育った西欧文化の価値感をもつきはなしてながめ,キリストより仏陀のほうがすぐれているといったり,近代西欧の生き方(パワー・ポリティクス)よりも中国人の自制と寛容の態度のほうが基本的にすぐれている,と主張したりした。西欧近代の現実を批判した彼の姿勢に,西欧近代の最良の理念が生きていたともいえよう。(市井三郎)


