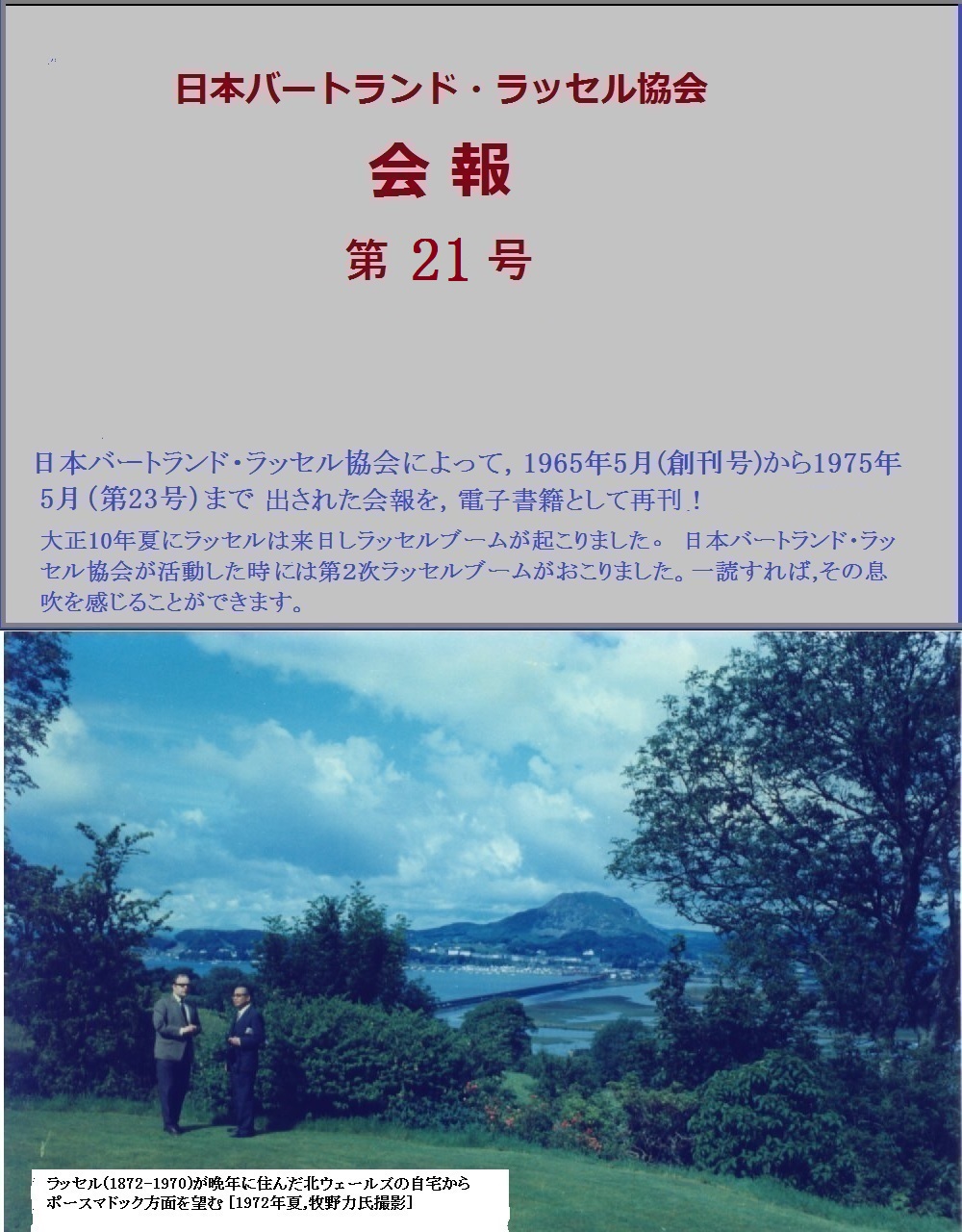碧海純一「バートランド・ラッセルの倫理思想の一断面 -ラッセルにおける認識と価値判断-」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第21号(1972年4月)pp.2-3
* 碧海純一氏は、当時、ラッセル協会常任理事、東大法学部教授<

(まえがき) 昨年十二月三日本会の研究会で、「ラッセルの倫理思想」と題する報告をする機会を与えられた。その折の報告を要約して本会報に載せることをも考えたが、幸い、永井成男教授が前号の巻頭言でラッセル倫理学説の根本にふれる卓見をのべておられるので、その驥尾に付してこの小論を草することで、責をふさがせて頂いた次第である。
永井成男>(1921~2005)教授は、本会会報第20号の巻頭言「理論と実践」において、ラッセルのメタ倫理学的立場に対して、興味ある分析を加えられた。その中で教授が、言及しておられる「二人のラッセル説」や、ラッセルの理論と実践との間には「単に心理的な関係しか存在しない」という見解は、ともに私も約11年前に書いた小著『ラッセル』(思想学説全書、勁草書房、1961年)において表明しておいたところであるので(前者については、たとえば、同書194ページ、後者については、35べージ以下)、多少の責任を感じ、ここに卑見を述べたいと思う。
初期のラッセル(大体1910年代以前)が典型的な直観主義型客観主義を奉じていたこと、ならびに、1920年前後にサンタヤーナの批判に触発されて価値情緒説に転向したことは、永井教授の指摘のとおりである(本会会報20号1ぺージ上段-なお、碧海前掲書、126~131ぺージ) 。問題は、やはり同教授の言われるように、ラッセル晩年の著作『倫理と政治における人間社会』(1954年/邦訳書名『ヒューマン・ソサエティ』)において、情緒説の立場が「不変」であるのか、それとも、「自然主義的傾向への推移」があるのか、という点である。この点について、同教授は「後説」の立場をとっておられる。結論から先に書くならば、私も永井教授の説に基本的には賛成である。特に、同教授が、ラッセルのある意味での自然主義への接近を指摘しつつも、かれの立場が終生にわたって自然主義的一元論とは明確な一線を画するものであったことを強調しておられる点については、全く私も同感である。ただ、本稿で私が指摘したいのは、一元論でない(すなわち、二元論的な)自然主義というものはそもそも原理的に価値情緒説と両立しうるものであり、現に、第二次大戦後の四半世紀における英米倫理学説の発展において主流をなしてきたものは、この意味での自然主義(特に功利主義)と情緒説とを自覚的に結合しようとするさまざまの試みではなかったか、という点なのである。
そして、「自然主義」という概念を、通常の理解に従って、「事実から価値を導く」ことが -もっと正確に言えば、「経験的事実に関する言明のみから成る前提群から価値言明を演繹する」ことが- 可能であることの主張と解するならば、「二元論的」自然主義と情緒説との結合形態は基本的には、やはり、情緒説の一種として分類すべきものであると私は考えている。というのは、情緒説が「主観主義」または「相対主義」として客観主義(すなわち、自然主義と直観主義)に対置されるゆえんは、前者が価値判断の究極的な主観性・相対性すなわち、客観的に証明されえないことを認容する点にあるからである。
価値判断の究極における主観性の認容は、しかし、決して、情緒説の批判者がしばしば非難するように、「タデ食う虫も好きずき」流の倫理的無責任と同義ではない。ウィーン学団時代の文献の中には、たとえば、A.J.エヤーの『言語・真理・論理』の初版(1936年-ちなみにこのときエヤーは26歳であった)や初期のカルナップの著作などに見られるように、木で鼻を括ったような言辞が散見しないわけではない。しかし、これらは、いずれも、倫理学を正面からとりあげた労作ではなく、むしろ、一種の obiter dicta(松下注:判決の時の判事の付随的意見のようなもの) にすぎない。分析哲学の流れの中から、本格的な倫理学文献が出てきたのは主として第二次大戦後であり、戦中に出た C.L.スティーブンソンの『倫理学と言語』(1944年)はその先駆をなすものであった。そして、この方面での戦後の発展は、事実言明と価値言明との基本的異質性をみとめた上で、いわば、両者をどう架橋して行くことができるか、また、両者をミックスしたディスコースの論理がどこまで精密化されうるか、という問題をめぐって進められてきた、といってよいであろう。ラッセルは、倫理的価値判断が、趣味などの問題とちがって、一般性の要求を伴っていることをすなわち、たとえば、「戦争は悪である」というとき、単に 'I disapprove of war' というだけでなく、同時に 'Other people should feel the same way' という要請がふくまれている-早くから主張しており、倫理的な価値言明についての合理的基礎づけが、一定の程度まで、可能かつ必要であることをみとめていた。1954年の『倫理と政治における人間社会』はこの方向へのかれの努力の結晶と見るべきであり、そこにかれのメタ倫理学的立場の『第二の転回』があるのではなくて、むしろ、中期以後の価値情緒説の当然の発展が見られるのである、と解すべきであろう。
私自身も、メタ倫理学上の立場としては、情緒説と自然主義との自覚的な、したがって二元論的な結合が妥当であると信じている。何となれば、この立場をとるものは、価値判断における原理上避けられない主観性の要素を率直にみとめつつ、可能なかぎりにおいて倫理的問題について間主観的・合理的なディスコースを堅持しようという姿勢をとるからである。幾何学の厳密性がプリミティヴな命題としての公理の証明不可能性の自覚にはじまると同じように、倫理学においても、不可避の主観性をみとめることが実は真の客観性への鍵を提供してくれる。マックス・ヴェーバーが半世紀以上も前に力説したように、本来主観的でしかないものに「客観性」のヴェールをかぶせて人前に出す「擬似没価値的」なやりかたこそ、客観性の最大の敵である。倫理的間題についての責任ある議論と学者としての知的廉直をともに重んずる人々-ラッセルやウェーバーはその典型である-は誰しも基本的にはこの点をみとめるであろう。
以上、永井成男教授の御発言に示唆を得て、ラッセルの倫理学説に関する私見の一半をここに披露した。いうまでもなく、私の趣旨は、永井説に対する異論を唱えるのではなく、むしろ、同教授の見解に賛同する立場から、それにいわば側面から支持を提供しようとしたところにある。同教授をはじめ、本会会員諸賢の御叱正を得れば幸いである。