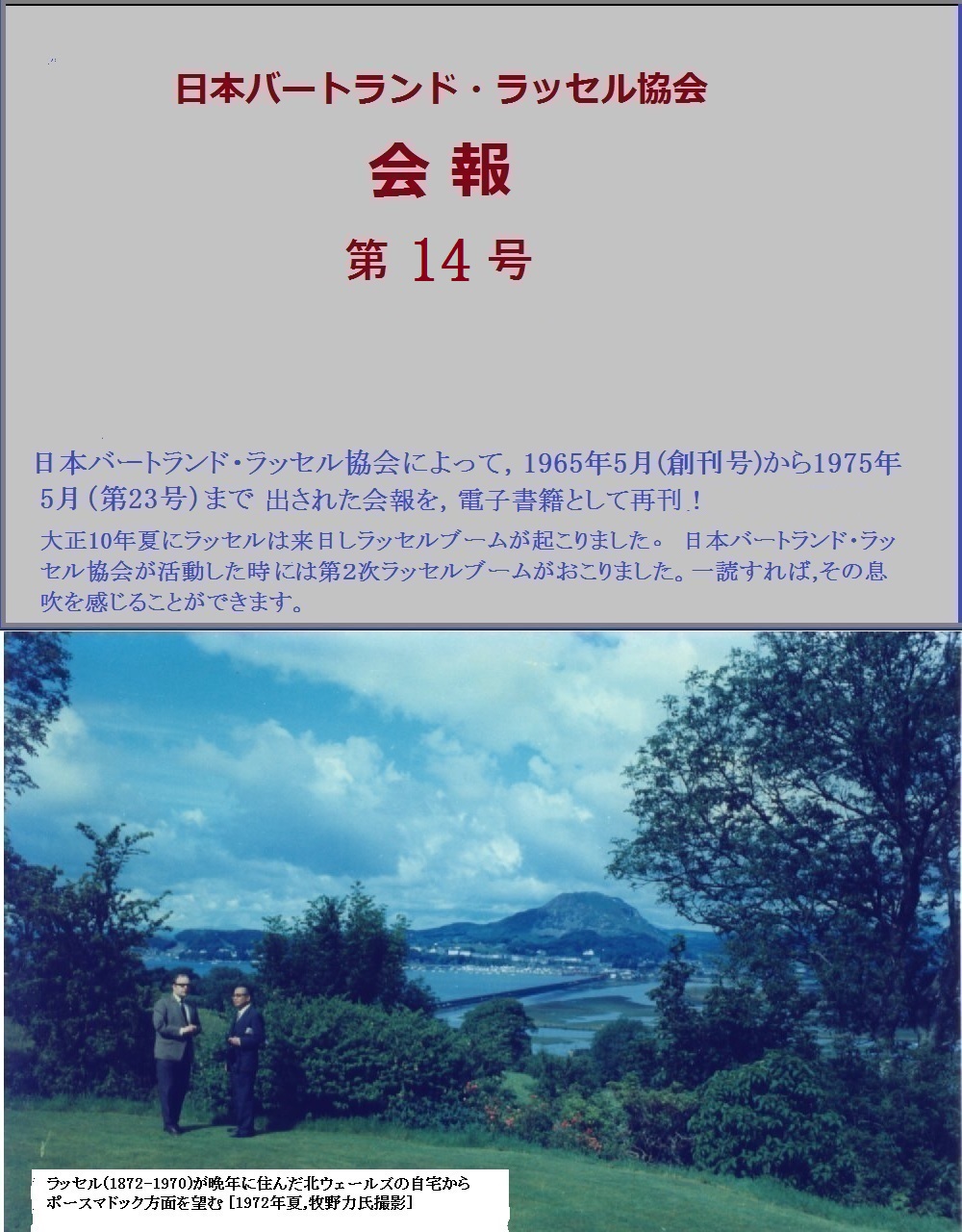碧海純一「バートランド・ラッセルの訃に接して」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第14号(1970年3月),pp.2-3.
* 碧海純一,は当時、東大法学部教授。本文は、1970年2月8日記。
 (1970年)2月3日の朝、自宅で調べものをしていると、2、3の新聞社や通信社からあいついで電話があり、ラッセル翁が逝去されたことを知った。なにぶん、この5月には満98才になろうというほどの高齢でもあり、いつかこの日の来ることは予期していた私だが、やはり現実に計報に接してみると、100才までは生きてほしかった、という気持を押えることができなかった。しかし、大正生れで、人の死ということになると、感情を押えることのできない私としては、自分でも不思議なほど冷静に訃報を受けとめることができた。これは、おそらく、ラッセルに対する私のかかわりあいが、ほとんど全くインパーソナルな、思想上・学問上のものだったことによるのであろう。私は、勁草書房から小著『ラッセル』を出した直後、みずから30ページほどの英文抄訳をつくって翁に献呈し、その折、好意ある手紙をもらったことがあるほか、2,3度書簡を交わした程度で、直接の面識は全くない。
(1970年)2月3日の朝、自宅で調べものをしていると、2、3の新聞社や通信社からあいついで電話があり、ラッセル翁が逝去されたことを知った。なにぶん、この5月には満98才になろうというほどの高齢でもあり、いつかこの日の来ることは予期していた私だが、やはり現実に計報に接してみると、100才までは生きてほしかった、という気持を押えることができなかった。しかし、大正生れで、人の死ということになると、感情を押えることのできない私としては、自分でも不思議なほど冷静に訃報を受けとめることができた。これは、おそらく、ラッセルに対する私のかかわりあいが、ほとんど全くインパーソナルな、思想上・学問上のものだったことによるのであろう。私は、勁草書房から小著『ラッセル』を出した直後、みずから30ページほどの英文抄訳をつくって翁に献呈し、その折、好意ある手紙をもらったことがあるほか、2,3度書簡を交わした程度で、直接の面識は全くない。
ラッセルの偉業とその意義については、某新聞紙上でも略記したし、いままでたびたび書いてきたので、ラッセルについてはすでによく御存知の本会報読者の方々を前にそれをくりかえすことは避け、私の感想を率直にのべさせて頂くことにしたい。
ありのままにいえば、ラッセルの訃を知ったとき、「悲しい」というよりもむしろ「羨ましい」という気持が私をとらえた。極限すれば、何か「さわやかな」感じがした、といっても、決して故人に対して礼を失したことにはならないであろう。それほどラッセルの一生は偉大であり、97年という異例の長寿にもかかわらず、最後まで異常なほど充実したものだったのである。すべての既成宗教や、手がるな「安心立命」を約束する擬似哲学を終始拒否したこの巨人は、若いころから自分個人の利害を超越し、宇宙について、人間について、人類の将来について思索しつづけ、その結果、自己の生死をも問題としない大悟徹底、西洋流にいえば equanimity の境地に到達していたのではあるまいか。
半世紀前、北京の病院で肺炎のため、生死のさかいを彷徨したときの記録も、すでにこのことを示唆しているが、まして、白寿になんなんとして死に臨んだラッセルは、おそらく、ソクラテスのような明鏡止水の心境で死を迎えることができたのではないか、と私は想像する。
ラッセルは、一方は、人間、社会、歴史、というようなヒューマンなことにだけ関心を示し、宇宙、自然の悠遠宏大な諸相とそこにおける人間の位置についてのヴィジョンを欠くような哲学者を「宇宙への不敬」のかどで批判したが、同時に、ミクロコスモスとしての人間の知性が、渺たる肉体の制約にも拘わらず、成就しうる偉業に対しても、心からの賛嘆を惜しまなかった。そして、不屈の情熱と稀代の知性とがひとりの人間においてむすびつくとき、どのような偉大な思想が五尺の身から生れうるかということを、そして、偉大な思想が王冠に依らず、剣に頼らず、幾百万の人々を動かしうるということを、身をもって示した点でもバートランド・ラッセルは人類史上忘れることのできぬ思想的巨人であったということができよう。
Requiescat in pace! (安らかに眠りたまえ)