林達夫「バートランド・ラッセル(著)『西洋哲学史』v.1(古代)について」
* 出典:『思想の科学』v.3,n.1(1946年 月)掲載* 原著:A History of Western Philosophy, 1945.
* 林達夫(はやし・たつお:1896~1984):評論家、編集者、ジャーナリスト/第2次世界大戦中、『思想』(岩波書店)の編集委員、戦後は中央公論社の出版局長、平凡社の編集長を歴任。明治大学において,ジャーナリズムの講義。
* (明治大学中央図書館)林達夫文庫(和書5,035冊、洋書4,657冊、和雑誌3,841冊、洋雑誌642冊)

|
ラッセルは、論理学の専門的な論文や著書においては専門家でないと読解困難なものを書いている。しかし、それ以外では、理論哲学も含め、一般的教養と知的好奇心のある人間であれば大部分の人が理解できるような書き方をするよう努力している。哲学は一部の専門家のためだけでなく、広く一般の人のためのものであるべきであるというのがラッセルの信念である。林達夫氏は'学問の厳しさ'についても言及されているが、それはラッセルにとっても同様である。分かり易く書くことも能力のうちであり、分かり易く書けないことを、学問の厳しさのせいにする人がたまにいるが、それは潔いとは言えないだろう。
林達夫氏によるこのラッセル(著)『西洋哲学史』の「批評・紹介」は、本来の意味での「批評・紹介」になっていないが、ラッセルのホームページ用の電子掲示板に、「ラッセルの『西洋哲学史』を読もうかどうしようか迷っているが、'林達夫氏の批判'が気になる・・・」との書き込みがあったため、ご紹介したしだいである。(2003.09.28, 松下)
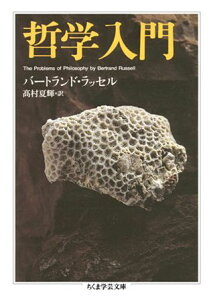
|
その私がバートランド・ラッセルの最近著である『西洋哲学史』を披見する気になったのには,省みるに2つの動機がある。いづれもつまらぬ,一寸とした動機だが,1つはこの5,6年間,西洋の学問の新しい段階とか風潮とかに直に接触する機会がなかったせいか,そういうものに対する飢渇が異常にたかまってきていたということである。たまたまラッセルの900頁に垂ん(なんなん)とする大著が目の前に置かれてみると,ついつい手に取ってみる衝動を禁じ得なかった。ラッセルという名前が私にとってはこれまでのところ文字通り1つの名前にすぎなかったという事も少しは手伝っていよう。彼は私などの大した関心を持たぬ方面における大家であるということを知らされていただけで,つまりは自分の食指を動かしてみる気になれぬ表題の書物ばかり書いている哲学者兼数学者であった。その学者が私自身にとっての中心的関心である歴史の領域にとび込んで来たのだ。『タイム』1945年12月17日号は、そのアメリカ合衆国にあらわれためぼしい書物を総評しているが,その中でラッッセルがこんな冒険を敢えてしたということを,私は初めて知って好奇心を喚起されていたのだ。現代の大哲学者にして哲学史の畑に這入ってした仕事に多少とも私が興味をもてそうに思われるのは,アンリ・ベルグソンがコレッジ・ド・フランスでやった,未刊の講義であるが,これは古代哲学者たちと彼がどんな対話をしなければならなかったかに興味の中心があるのである。チボーデの「ベルグソニスム」などから推測すると,それは多分死者との格闘であり,一種の検屍であるらしいが,その対決は,彼の新しい哲学の市民権獲得のために不可避的に要請されたものらしい。ラッセルの哲学史への進出は,かかるベルグソン的場合とは全然違うようだが,ではそれは何であろうか。
ラッセルの書物に私が惹かれた第2の理由は,つまりその「何」に答えるかのように,その表題の下に,彼の西洋哲学の歴史が政治的社会的環境とのつながりにおいて取扱われている旨が特記されていることであった。私は1931,1932年のころ三木清,羽仁五郎,本多謙三と4人で、『社会史的思想史』という題目の下に西洋思想に関する一連の共同制作をしたことがある。岩波講座『哲学』においてであった。これらの勤勉な俊英たちのあいだに伍して,怠慢凡庸な私が受持ったのは事もあろうに中世であったが,ただでさえ困難なこういう角度からの思想史への切り込みはこの場合実に難渋を極めた。そこは殆ど未耕地といってもよかったからである。日本の事情においても,西洋の事情においても,しかしちょうどその叙述を半分ばかり書き上げたとき,都合のよいことにソヴェート・ロシアの歴史家であるロフ,ヨアニシアニ共著の『唯物史観世界史教程』第2分冊『封建制度』なる書物の邦訳が白揚舎から出版された。私は大なる期待をもってこれを読んだが、封建主義の一般的本質を論じたヨアニシアニの書いた部分を除き、他はまるでお話にならぬほど杜撰(ずさん)にして粗雑極まるものであってひどく期待に外れた。殊にその第11章,「封建社会のイデオロギー」の如きは,むしろ悲惨な1つの学問的カリカチュアであるというほかに言葉がないほど言語同断なものであった。当時かの国の文化革命の課題となっていた封建的遺制との闘争,宗教との闘争のための遠回しの通俗的パンフレットとしか思えなかったくらいだが,それにしてもその歴史的事実の歪曲と侏儒化との工作は度を過していた。妙なことに、この下らぬ書物が私を支え励ます役割にまわる羽目になり、私に自信をつけてくれたのである。
この仕事は、私にとっては1つの有益な知的訓練であった。こんど羽仁五郎と一緒に相談して,1つには今は亡き三木清、本多謙三の思い出のためにもと,この共同制作を単行本として刊行することに取り極め,自分の,また公式主義的生硬さを脱しきれずにいる,未熟な労作を世に問うことになったが,この14,15年前に書かれた共同制作が,今日なおまだ少しでも存在理由をもつかどうか,それを測定するよすがとするためにも,この一種の社会史的思想史たることを標傍しているラッセルの最近の著書を通読してみたい気がしたのである。そしてその結果は,幸か不幸か,我々の共同制作は,その多くの欠陥にも拘らず,未だ十分刊行するに足るものだという結論を得たのである。それはいづれは後からくる人々によって踏み越えられねばならぬ書物ではあるにしても,しかし稽古台には当分のうちはまだ結構役立つであろう。稽古台的な書物があまりにも不足していることを、しみじみ痛感せざるを得ないのだ。
取りあえず私は、ラッセルの書物の古代の部を読んでみた。そして実は正直に云うと、途中で段々読む興味を失って,プラトン以後はとびとびに目をさらすだけで抛擲(ほうてき)してしまったのである。中世以後のことは知らない。古代の限りでは、ラッセルは結局歴史家ではない、たかだか初歩的な年代記者たるにとどまっている(松下注:ラッセルは、西洋の歴史、あるいは「広義の」思想一般の歴史を書いているわけではなく、哲学・知の歴史を必要最小限の政治的社会的連関のもとに記述している。)。ひと昔前,文藝とか何とかの社会史的考察なるものがはやったことがあった。チョーサーとその時代的背景といった風な、それは木に竹をつぐといった甚だ簡単な機械的操作によって作られていた歴史叙述であった。ラッセルの書物は、遺憾ながらそれを想わせた。時代の政治的社会的構成とそのダイナミックとを語る際には,例えばバリーやロストヴェチェフの古代史により,そして哲学者とその哲学の叙述にはバーネットやヘヴァンの哲学史的叙述を参考にという風に,これは根本的にいえば、学生などが卒業論文の執筆に際して意識的・無意識的に使う,また通俗的な概説書などに著しく見られる最も幼稚な,また最も安易な,紋切型である。ラッセルの文体は簡潔,明快で、その筆致の限りでは popularizer としての資格を申し分なく具有しているといえる。しかしこの『西洋哲学史』が一般的啓蒙、通俗化のために書かれたことはあるにしても、このような古臭い常識的な歴史的操作法の上に安住していることは,私にはそれがラッセルであるだけにちょっと解せない。以前別の見地からではあるが,フランスのすぐれたギリシア哲学研究者であるアルベール・リヴォについても,同じような失望を感じたことがあった。「戯曲2プラトン」その他一連の,あんなにも立派なプラトン研究を書いた彼が,『古代思想の大潮流』という通俗化の書を著わす段になると,妙に調子を落とした,卑俗に堕落した「参考書」風な書物を書いて平然としているのであった。総じてこんどのラッセルの『西洋哲学史』の古代の部ではバーネットの古代哲学研究の成果が,ことにフランスのが,十分には取り入れられていないように見受けられたことも,私には不満のたねの1つであった。私はその方面のみに没頭している研究家ではもちろんないし,それに我が儘なしかも怠惰な読書家にすぎない。それでもレオン・ロバンの『ギリシア思想』(1923年)やブレイエの『哲学史』(1926~1928年),『ブロチンの哲学』(1928年)の出現似後に読んで多大の感銘を受け,収穫を得た書物が決してなくはないのである。
1つはレオン・ブランシュヴィックの『知能の各時代』(1934年)という,これは甚だ難解な,手ごわい書物である。その第1章「叡智的なるものの偏見」,第2章「非合理的なるものの幻影」及び,第3章「ロゴスの世界」(L'univers du discours)が大体古代に当たる時期の哲学思想を取り扱っている。殊に「叡智的なるものの偏見」においては、若しレヴイ・ブリュールの用語に従って「原始的心意」(mentalite primitive」と呼んでいいものを文明時代以前に認めうるなら,ブランシュビックは,正にそのものと古代的思惟との関係を執拗に究明しようとしていて,これは甚だ示唆的であった。原始的心意がギリシアにおいていかに継承されたか――というのはいかに変改されながら心的遺制として,残存されたか,そしてそれがいかにして現代の吾々の頭脳の中からさえ完全に失われていないか,これは特に今の吾々にとって時事的な意味もなくはない,興味のある問題の1つであろう。そしてこれは呪術より技術及び科学へといった,フレーザーやユベルニモスなどの問題の立て方では従来ほとんど発掘することのできなかった広大な心的領域の存在していることを思わせ,それらの方式への単なる問題還元では事は決して片づかないことを示している。ブランシェヴィックの書物からこの問題を受取って以来,古代思想のことを取り扱った書物にぶつかる毎にその入口の敷居のところではたとそれを思い起すことが例となってしまったが,ラッセルの書物では,恐らく哲学史の冒頭における重要関心事である,この問題の存在さえ誰にも気付かせないように素通りしていきなり中へ入ってゆく。この問題は私によれば,哲学の先史時代から歴史時代に入るための禅院の玄関のようなもので,しかも文字通り「玄関」である。だからそれを知った今となっては私はこの玄妙な難関を,それが難関であることも知らぬげに中へ入って行く哲学史家を,もはや哲学史家としては認めようとは思わなくなっている。その玄関がするするとわけなく越せるからといって,人はいきなり中へ入って行くことが許されるだろうか。私なら許す気が毛頭ない。私ならそんなことをすれば見えざる棍棒で一撃を受けて「止まれ」を喰うであろう。そして恐らくこの玄関で立往生してしまって,額に油汗がしみでるほど散々に苦しみ抜くことであろう。それが学問というものだ。学問とはそんな難題に充ち満ちているものなのだ。
これは先史時代,またはエドウアルド・マイヤー風にいえば,「人類学」から歴史的時代,そしてアンリー・ベール及びデュルケェム風にいえば,氏族から帝国へといった歴史的学問の甚だむづかしい問題以上に遙かにむづかしい問題といえる。原始的心意についてある厖大な数々の大著を遺して死んだレヴィー・ブリュールは,同時に,それ以前にはすぐれた哲学史家として立ち現われていた。だから彼は当然,原始的心意と古代哲学との架橋という,この巨人的な仕事をもなすべき第1の有資格者であったし,それに義務負担者でもあったのだ。この遺された仕事を,今後の古代哲学研究家は是非とも果たさなければならぬ。難題だけに取っ組み甲斐があろうというものだ。
私が非常に刺激を受けた書物の第2のものは,ピエール=マキシム・シュールの『機械文明と哲学』(Machinisme et Philosophie) である。この学者は,『ギリシア思想の成立についての試論,プラトン哲学研究への歴史的序説』という興味ある題名の書物を1934年に書いているが,これは残念ながら私はまだ読むに至っていない。しかし1938年に刊行された『機械文明と哲学』は,思想史の領域における通俗的叙述としては,甚だ出色のものと断言して差支えない。これは,機械文明の発展が論理上古代以来既に可能であったと考えられるに拘らず,何故にそれが阻止せられたかの理由を究明することから出発して,ギリシア人並びにローマ人に深く根差していた一連の嫌悪感のようなものを掴み出し,その全体を,シュールは,「前機械的」或は「反機械的」心意(mentalite premecanicienne ou antimecanicienne) と呼ぶことによって,このものの成立の社会的根拠の探求とその発展と解消とのその後の成行の説明とを企てているのである。その最初の部分である第1章,「古典的古代と機械文明」及び第2章「1つの新しい心意へ」については,私は殆ど異論なくその水際立った捌き(さばき)ぶりに承服する。古代世界の奴隷所有的社会構成がいかにして前機械的乃至反機械的心意を産み出し,そしてこのものを普般的な心理的習性にまで定着して行ったか,という問題の提起とその究明とは,古代社会における社会史的思想史の最も興味ある題目の1つであろう。そしてこのような問題は,例えばヘルマン・ディールスの『古代技術』においても,またアベル・レエの3冊の大著『古代における科学』において十分には取扱っていないものなのだ。若し私が誰からか西洋思想史の入門書として,先づ何を読むべきかという質問を受けたとするならば、その第1に挙げる書物は恐らくこれであろう。従来の史的唯吻論の立場から書かれた思想史は,殆ど例外なく正面切った「イデオロギー」の社会史的究明に終始していて,こうした「心意」の,より微妙な,しかし或る意味からいえばより重要で,より根本的な問題の所在とその究明とを忘れている。思想の世界は巨大な心理的遺制の棲処(住処:すみか)である。思想革命の達成は,この心理的遺制の撲滅に比べると実にたやすいともいえる。シュールの書物は,そのことを明快に教えているといえる。――驚くべきことには,(否,これは当然のことかも知れぬが)ラッセルの『西洋哲学史』は,こうした問題についても何ひとつ語っていないのである。
もう1つ私を大いに教えてくれた書物がある。ジェラール・ワルテルの『共産主義の歴史』の第1巻(1932年)である。その第2部がギリシア及びローマを取扱っている。第1巻の限りでは,これは事の次第上,ユートピア思想史と呼び更えても一向に差支えないものである。これは問題の所在もその重要性も,以前から知られている領域のものに属するから,力説するまでもなかろう。この書物のプラス(松下注:+)はその資料収集の豊富さと,先行学者の業績の丹念な紹介とにある。人口に膾炙(かいしゃ)されているマックス・ベーアの『社会主義及び社会闘争の全史』などは,その足許にも及ばない。この書物のすぐれているのは,むしろ第1部のユダヤ及びキリスト教的起原を取り扱った部分ともいえるが,にもかかわらず第2部も一読の価値は十分にあると思う。ギリシア各都市における階級闘争を取扱った生き生きした各章を(長所はそれとは別にあるのだが),例えばラッセルに散在する同様の叙述と比較してみるがよい。バリーやロストヴチェフからのセコンド・ハンドの干乾びた,死んだ叙述がいかに味気なく思われることか。
だだ1つ,ラッセルの名誉のために言っておくが,こんどの書物で私の印象に深くの残った箇所があった。それはピタゴラスを取り扱った短い1章である。 ピタゴラスは古代哲学における最も重要な1章であるが,しかしこれほど謎の如く理解に困難な哲学者とその業績もないものだ。さっきあげた本の中から例を引くが――ロバンの『ギリシア思想』でも,ワルテルの『共産主義の歴史』でも,長々とピタゴラスとピタゴレアニズムを取り扱っているが,結局どうもあまり私には要領を得なかった。私にとっては,数学と神秘主義とは最も苦手な相手であるせいもあっただろう。しかしラッセルのこの短い章は,とにかくこれまて読んだピタゴラスに関するどの文章よりも面白かったことは確かである。鮮かな冴えた切り込み方を,しかも楽々とやってのけている。この楽々と書いてのけていることは,書物の読んだ限りの部分ではどこにでも至るところ感じたことで,そこに大家の風格とでもいったものを認めることにやぶさかないが,洞察の鋭さの点で大家を感じたのは,古代の部の限りではこ「ピタゴラス」の章の,しかも最後の1節に当たる18行,アメリカ流にいえばきっかりその101語だけであった。それを全訳してみると、こういう風である。
「ピタゴラスと共に始まった数学と神学との結合は,ギリシアにおける,中世における、そしてカントに至る近代における宗教哲学を特色づけた。ピタゴラス以前のオルフィズムは,アジア的な密議宗教に類似していた。しかしプラトン,聖アウグスチヌス,トマス・アキナス,デカルト,スピノザ及びカントにおいては,宗教と推理との,無限なるものへの倫理的渇望と論理的讃美との,内密な融合があって,このものはピタゴラスに発し,ヨーロッパの知的にされた神学を、アジアのもっと単刀直入的な神秘主義から区別しているものである。どこでピタゴラスが間違っていたかをはっきり言えるようになったのは,実は極く最近のことである。思想の領域において彼ほどに影響力のあった他の人間がいたということを私は知らない。私がこれを言うのは,プラトニズムと見えているところのものが,分析すれば,本質においてピタゴレアニズムであることがわかるからである。感覚にではなく,知性に対して啓示せられた,永遠の世界という全観念は,彼に由来している。けれども彼のために,キリスト教徒がキリストを「言葉」として考えたのではなかったろう。けれども(松下注:けれどもまた、)彼のために,神学者たちが神と霊魂不滅との論理的証明を求めたためではなかったろう。けれども彼のうちに,このすべては以前含蓄的である。いかにしてそれが顕現的になったかはやがて見られる通りだ。」これはそれだけで優に1冊の大著に値する実に多き問題提出であるに違いない。ラッセル自身がこのテーマを果たして成功的に展開し,解明しているかどうか,――これはこの書物全体を通読してみないことにはわからない。しかしそれにしては,入門者向きにあれもこれもと何から何まで語って聞かせようとしていた懇切なラッセルの歴史叙述は,私にはこうるさくて煩に堪えない。いっそのこと,このテーマを一筋に迫及した1冊の書物があって欲しいものである。
