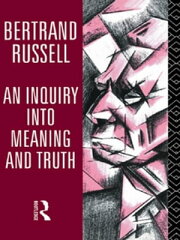毛利可信「バートランド・ラッセルの言語観について」
* 出典:バートランド・ラッセル(著),毛利可信(訳)『意味と真偽性-言語哲学的研究』(文化評論出版,1973年1月。417pp.)* 原著:An Inquiry into Meaning and Truth, 1940.
*(故)毛利可信氏(もうり・よしのぶ 1916-2001)略歴
同・邦訳書-付録1より(1972年7月31日)
コトバは第1に、ふつうの人がふつうの場で使うのである。従って上記の「公理」にあたる約束ごとが天下り的に定義されるのでは不都合が生ずる。つまり、コトバの世界と外界との間のギャップを何とかして埋めなければ、コトバの機能の説明ができないわけである。そして、そのような、コトバ対外界の対決(真偽問題の基本線)のギリギリの所は、「これは青い」「シカゴは大きい」などの文であって、「これらの文が signify する命題」が真であるか、偽であるかを、どうして「知る」のか、そこが問題である。LP の人たちは①「シカゴが大きいとき「シカゴは大きい」という文は真である」と言い、知識とは、たとえば②「鉄は水に沈む」などのようなものについて考えられるものだ、と言う。
ラッセルに言わせれば、これはとんでもない話である。上の①などは、同語反復以外の何物でもない。そんなことでよければ、人は「今、これこれだから「これこれだ」と言うのだ」という調子で、何を言っても強引に自分の発言が真だと言えるはずである。ひとつの語が出てくる契機はいろいろある。その中である状況が、他の語を介さずに、直接的に、たとえば hot という語を喚起するとき、'This is hot.'が真である、というように、感覚で直接とらえ得るもの(後述の 1ogcial atomism 参照)に対するコトバの段階から着実におさえていかねばならない。
また、上の②は、全称命題であって、これは推論の結果到達されるものである。従ってその推論のもとになる知識が先決問題でなければならない。LP の人たちは、ここを飛び越した段階から議論をはじめているのである。人は、単一の経験からも、直接的に何かを「知る」のである。もしそうでなければ、ゼロに何をかけてもゼロだから、高度の知識などあり得ようはずはない。このようにしてラッセルは、まず語の説明を与え、次に語を組み合せて文を作る段階になる。そのとき、文が、各語の meaning をふまえて、その上に、統一的なまとまりを持っているという点の説明が必要になる。そこでラッセルは「関係」を説明し、「関係」を確定するパターンとしての原子形式を考え、これに適合した命題を signify する文を原子文と呼ぶ。次に原子文を or などで結合すれば分子文となる。また文中に、some, all などがあらわれるような「一般化」(松下注:量化)を考えることになる。
このように、外界に何かがある、ということと、それを知覚し、それを知識としてまとめることとは別物である。いわば、「知覚のフィルター」を通すということは、外界をわれわれが切りとるにあたって、何らかの操作(たとえば、抽象化、視点の設定)を行なうことを意味する。本書でしばしば繰り返される説に「陳述文を主張した場合、それは、主観面では、話者の心的状態(Belief)を表現し、客観面では、事実を指示する」というのがある。この説は,発言の場に「事実とコトバ」があるだけではない、コトバは人間の心の中を炉過して出てくるものだ、つまりは、知覚のフィルターを通しているものだ、ということを指摘しているのである。
A氏が①'John is tall.' という主張をしたとする。このとき、この文が signify し、express するものはそれぞれ「John is tall」なる命題、および、この命題がA氏の Object of Belief であることである。A氏がこの Belief を持つとき、A氏は 'John is tall.' と主張するのであって、それはA氏が 'I believe that John is tall.' と発言することを意味しない。'believe' という語が出てくるのは、A氏の①なる発言について comment する立場のもの(A氏自身でもよい)が、それを記述する――発話の原点を内省することを含む――ときである。つまり、第3者が、Mr. A believes that p. と言い得る場合に、A氏自身はその p を Belief として持ち、また本人は、(発言するとしたら)その p だけを主張するのである。believe, doubt, desire などが「命題態度」をあらわすというのはそういうことである。
上の考察は、さらに重大な問題を提起する。それは、人の発言行為もまた、一般の行為と同じようにわれわれの経験する事実の一部であるということである。LP にあっては、①外界、②コトバの世界、③メタ言語の世界、というように割り切った図式で考えるのを原則とするが,しかし、ラッセル流に考えれば、②も、従って③も、ある角度から見れば①の一部でもある。もちろん、ラッセルは、対象言語(一次言語)を定義し、それより上位の言語は論理語等の導入によって定義しているのであるから、'It is true that p.' 'p or q.' などは――p,q が一次言語であるとき――当然2次言語であるが、この2次言語は、いわゆるメタ言語ではない。(LP の言うメタ言語のことをラッセルは「第2階の言語」と言っている。) すると、ラッセル自身もことわっている通り、本書で扱う文の中には、論理言語としてのメタ言語は入らないのであるが、いわゆる「意味論的メタ言語」(Semantic meta-language)は含むものと解される。なお、この「意味論的メタ言語」は、部分的にはカルナップの言う Material Mode of Speech に属する。以上述べてきた、A氏の 'John is tall.' という発言と、第3者が言う 'Mr. A believes that John is tall.' との関係も、よく吟味すれば、これまた「外界に何かがある」ということと、「人の知覚のフィルターを通して何かが得られる」ということとの、根本的な区別の例証となっていることがわかる。このような事例は、本書の至る所で見られる。たとえば、'P is part of W.' についてもそうである。上の文中で、筆者が書いた 'Mr. A' という所で◎「'M' は 'A' の左にある」ということを言うのに、この文自体に「全体」を言いあらわす必要はない。発話者は 'M' も 'A' も 'Mr. A' の一部であることをふまえてはいる。しかし、◎を言うときに 'P is part of W.' を知覚する必要はない。これを知覚するとすれば、それは、'I believe that p.' とか、'I say p, because...' の場合と同じく、発話の原点について comment する立場をとったことをあらわす。
また、「習慣」と「全称命題」との関係についてもこのことが出てきた。このことは,言語の獲得も1つの習慣であることを考え合わすとき、意義深いものがある。筆者が犬に食事を与えるとき、その前にベルを鳴らすことに決めているとする。すると、その犬は「ベルが鳴っている」を信ずるときは、いつも「食事が与えられる」を信ずるようになるであろう。(コトバを持たない動物も Belief を持ち得ることをラッセルは指摘している。)このとき、上のいつもが「 」の外にあるのでわかるように、犬の Belief の中にいつもが入ってはいない。単に、犬がいつもそのようにするということ、つまり、犬の習慣がそのようだということである。しかし、筆者がその犬の行動を記述しようとして《この犬は「ベルが鳴っている」を信ずるときには、いつも「食事が与えられる」を信ずる》と言うときには,筆者の Belief は《 》の中のような命題であり、その《 》の内部にいつもがあるわけだから、これは全称命題である。
さらに、上述のように1つの文発言も、われわれの経験する、外界の事実だという観点から見るならば、この問題は、1つの文発言たとえば、①'Brutus killed Caesar.'と、②その文発言についてのシンタックスのコトバとの関係についても見られる。①'Brutus kilIed Caesar' の統一的意味――BがCを殺したのであって、CがBを殺したのでははない――を確定するものは、①の3語の語順である。この3語は「語順をもっている」のである。さて①の意味がこれこれだという根拠を説明しようとして、①の 'Brutus' をβと名付け、'Caesar' を γ と名付け(簡略のため、'killed' は無視しよう)、シンタックスのコトバとして、②'β precedes γ.' と言ったとする。すると、②の3語は「語順を主張する」のであるが、しかし、②の3語自身も「語順を持って」いる所が問題である。すなわち②を言う人は、*「β は γ に先行する」と言いたいのであるが、そういう意味はどうして確定するのか。①の意味を確定するために②を言う必要があるのならば、同じ理由で②の文に*の意味を持たすためにはさらに、③「'β' of ② precedes 'γ' of ②.」 というような文を言う必要があるという理屈になる。これでは「無限の後退」におちいる。
①の文には語順がある。これは外界に「順序」がある、ということである。「そういう語順がある」ということを、①の文自身は言う必要はない。その発言について comment するものが、シンタックスのコトバで、①の語順を、②で主張することはできる。しかし、②自身も語順をふまえて出てくるはずである。ヴィトゲンシュタインが、「シンタックスをコトバで表現することはできない」と言ったのは、このようなことを指すのである。ラッセルは、「階型(type)」に基づいて、上の「無限の後退」から脱却すべきことを説いているが、それは、素朴な発話と、それについての commentator 的発話とのレベルの相違を指摘しているのである。
ラッセルの、本書での立場を、あえて割り切って言うならば、それは、Logical Atomism (論理的原子主義)である。この考え方の根本には、この宇宙に存在するものは、直接感覚でとらえ得る patches of colour, sounds, smells, etc. のような Simples(単純体)のみ、ということがある。ここに机があったり、机の上に本があったり、筆者が教師であり、また一面父親であったりするのは、決して、そういう複雑なものがそれぞれ絡みあって、外界にあるのではなく、個体は単に a bundle of qualities(性質の束)としてあるのである。複雑な事実を作っていくのはコトバの世界の方である。また、'Brutus killed Caesar.' の説明に見られるように、外界にあるものは原子形式に沿ってあらわされるような、いわば「ナマの動作」であって、それに意味づけを行なうのはコトバの方である。(ただし、これはラッセルが極端な Nominalism(唯名論) を説いているということではない。一部の Nominalists は、「検証不能なことはすべて、コトバの約束ごとであって、外界に対応物を持たない」などと言う。ラッセルは、これに対し「あなたの奥さんは癌だ」と言われた場合を例にあげて反論していることを想起されたい。)ラッセルはこれに加えて、人間の言語活動もわれわれが経験する事実であるから、コトバの説明に心理的側面を重視すべきであると言っているのである。論理語である、not, or, some, allなども、論理学者のように、天下り的に、~,∨,(ヨx)(Fx),(x)(Fx)などを定義して、一切それに従って意味論でもシンタックスでもやるというのなら、ある意味ではスッキリするが、素朴な言語心理とは大きなズレを生ずる。そこで 'or' でも、'There's no cheese.' でも、キメ細かな心理的説明を導入して成功していることは、本文で見るとおりである。('or' は「ためらい」の表現として。'There is no cheese.' は 'There is some cheese.' を打ち消す気持、すなわち拒否、の表現として)
ラッセルの説に対する批判もいろいろある。たとえば,個体が 'a bundle of qualities' であるならば、個体の同一性――10年前の毛利が今日の毛利と同一人であるというような――が何によって保証されるのか、というような反論が(第6章の説明にもかかわらず)ある。このような論争も興味深いことではあるが、「言語の意味」の話からそれることでもあり、今ここではとりあげないことにする。
本書の中でラッセルの側からいろいろの疑問を提出している「カルナップの立場」を一言弁護すれば、争点の多くは、両者が目標ならびに発想を異にする所から来ているものと思われ、カルナップの論理体系は、それはそれとして、精緻を極めたものであると筆者は思う。ゆえに、それらの争点を含めて、ラッセルとカルナップ(それに後期ヴィトゲンシュタイン)は、互いに相補的な研究をしているのであると解したい。
最後に、本書の意義について示唆的であるのは、本書の発表時期である。周知のように、ラッセルの活動は第1次世界大戦頃を境としてその前は、数学、論理学方面が圧倒的に多く、それ以後は、社会的なもの、すなわち、平和とか幸福とかを論じたものが漸増的に多くなり、1950年以後はほとんど後者に限られる。これは、ラッセル自身が随筆「80歳の誕生日を迎えて」で述べているように、彼が少年時代から2つのことを人生の目的としたこと、すなわち、①人間は何かを「知り」得るのであるかを見出すこと、②より幸福な世界を作るためにできるだけの努力をすること、の2つの目的を追求してきたことのあらわれであって、38歳ごろまでは①を、それ以後は②を、努力目標とし、晩年に至って、この、①,②を統一的に扱うことができるようになったのである。Principia Mathematica(1910-1913) や Introduction to Mathematical Philosophy (1919)が①の時代の作であるに反し、本書は1940年の発表であり、それは、①から②へ移り、ようやく、この両者を統合的に考える時期である――このことが示唆的であると言いたい。ラッセル自身も、「自分の内面的失敗」について、上掲の随想の中で次のように告白している。
「私はプラトン的永遠の世界――そこでは数学が、ダンテ「神曲:天上篇」の最後の部分の持つような美しさで輝いている――に対し、多少とも宗教的信仰に近い気持を当初は抱いていた。しかし、後に、その永遠の世界は「実質のないもの」(trivial)であり'数学とは、単に、同じことをいろいろちがった語で述べる術に過ぎないとの結論に達した。(下線訳者)もちろんこの言葉は、数学や論理学の嫌いな人が、自分の数理嫌いを正当化するための口実に使うべきものでない。反対に、ラッセルほどの数理に徹した人が、この感慨を口にすることの意義を察知すべきである。単なる数理的考察にあき足らなくなったときに、ラッセルは、その解決をどこに求めたのか。本書の内容はそれを明らかにしているのだと思う。(昭和47年7月31日記 Y.M.)