*右欄上の写真出典:B. Russell and His World, by R. Clark, 1981.
使徒会(The Society) は,私の時代より少し後になると,いくつかの点でかなり性格が異なるものとなった。私の世代よりも10年ほど若い世代の傾向(風潮)は,主にリットン・ストレイチー(Lytton Strachey,1880-1932/右写真)とケインズ(John Maynard Keynes,1883-1946)の影響を受けて,定着した。この10年間がもたらした精神的風土の変化がいかに大きかったか,まさに驚くべきものがある。我々はなおヴィクトリア朝時代(ビクトリア女王在位:1837〜1901)の人間であったし,彼らはエドワード朝時代(エドワード7世在位:1901〜1910)の人間であった。我々は,政治と自由討議によって,秩序ある進歩をもたらすことができると信じていた。我々の間でより自信のある者が,大衆(民衆)の指導者となることを望んでもよかったが,誰もが大衆から遊離することを望むものはいなかった。ケインズとリットン・ストレイチーの世代(の人々)は,誰もペリシテ人(Philistine:昔パレスチナの南部にいた民族でユダヤ人の強敵−−ここでは教養のない人・俗物の意味で用いられている)と親密な関係を保ちたいと思うものはいなかった。彼らはむしろ,洗練された避難所で,心地よい情緒の中で,隠遁生活をすることを目ざし,(エリートにとって)'善'とは,エリートの閥(徒党)を相互に情熱的に賛美しあうことにあるという考えを抱いていた。彼らは,この信条は,−−まったく不当にも−−G.E.ムーアが創始したものだとし,また,自分たちはムーアの'弟子'であると公言した(松下注:日高氏は,Keynes の前にピリオドがあるのを見落とし,「ケインズの弟子」と誤訳されている。)。ケインズは,彼の回顧録『若き日の信条』(Early Beliefs)において,彼らがムーアを賛美し,また(同時に)ムーアの学説の多くを無視した,と語っている。ムーアは,当然おくべき比重を道徳においていたし,その有機的統一の学説により,善は孤立した情熱的な瞬間の系列(集合)から構成されるとする見解を退けていたが,自分たちをムーアの弟子であると考えていた人々は,ムーアの教えのこの側面を無視し,ムーアの倫理学を,息づまる女学校の感傷主義の唱道に落としめてしまった。
ケインズは,後にこうした雰囲気から脱出し,'大きな世界へ'出ていったが,ストレイチーはけっして抜け出さなかった。けれども,ケインズの脱出は,完全なものではなかった。彼は,どこに行こうと'世俗の中の僧正'の気分を常に携えて,世界中を歩きまわった。しかし,真の'救い'はどこか別のところ,即ち,ケンブリッジ大学における彼の忠実な信奉者たちの間にあった。彼が政治と経済に関係するときは,その魂をこの心の故郷に置いていたのである。それが彼の書くもののほとんどに,ある種の,堅く,けばけばしく,冷酷な特質がある理由である。(しかし)大きな例外が1つある。それは『平和の経済的帰結』という彼の著書である。それについては,すぐあとでもっと詳しくふれることにしよう。
|
Some things became considerably different in the Society shortly after my time.
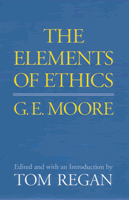 The tone of the generation some ten years junior to my own was set mainly by Lytton Strachey and Keynes. It is surprising how great a change in mental climate those ten years had brought. We were still Victorian; they were Edwardian. We believed in ordered progress by means of politics and free discussion. The more self-confident among us may have hoped to be leaders of the multitude, but none of us wished to be divorced from it. The generation of Keynes and Lytton did not seek to preserve any kinship with the Philistine. They aimed rather at a life of retirement among fine shades and nice feelings, and conceived of the good as consisting in the passionate mutual admirations of a clique of the elite. This doctrine, quite unfairly, they fathered upon G. E. Moore, whose disciples they professed to be. Keynes, in his memoir 'Early Beliefs' has told of their admiration for Moore, and, also, of their practice of ignoring large parts of Moore's doctrine. Moore gave due weight to morals and by his doctrine of organic unities avoided the view that the good consists of a series of isolated passionate moments, but those who considered themselves his disciples ignored this aspect of his teaching and degraded his ethics into advocacy of a stuffy girls-school sentimentalising.
The tone of the generation some ten years junior to my own was set mainly by Lytton Strachey and Keynes. It is surprising how great a change in mental climate those ten years had brought. We were still Victorian; they were Edwardian. We believed in ordered progress by means of politics and free discussion. The more self-confident among us may have hoped to be leaders of the multitude, but none of us wished to be divorced from it. The generation of Keynes and Lytton did not seek to preserve any kinship with the Philistine. They aimed rather at a life of retirement among fine shades and nice feelings, and conceived of the good as consisting in the passionate mutual admirations of a clique of the elite. This doctrine, quite unfairly, they fathered upon G. E. Moore, whose disciples they professed to be. Keynes, in his memoir 'Early Beliefs' has told of their admiration for Moore, and, also, of their practice of ignoring large parts of Moore's doctrine. Moore gave due weight to morals and by his doctrine of organic unities avoided the view that the good consists of a series of isolated passionate moments, but those who considered themselves his disciples ignored this aspect of his teaching and degraded his ethics into advocacy of a stuffy girls-school sentimentalising.
From this atmosphere Keynes escaped into the great world, but Strachey never escaped. Keynes's escape, however, was not complete. He went about the world carrying with him everywhere a feeling of the bishop in partibus. True salvation was elsewhere, among the faithful at Cambridge. When he concerned himself with politics and economics he left his soul at home. This is the reason for a certain hard, glittering, inhuman quality in most of his writing. There was one great exception, The Economic Consequences of the Peace, of which I shall have more to say in a moment.
|


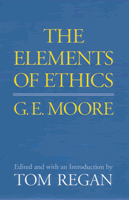 The tone of the generation some ten years junior to my own was set mainly by Lytton Strachey and Keynes. It is surprising how great a change in mental climate those ten years had brought. We were still Victorian; they were Edwardian. We believed in ordered progress by means of politics and free discussion. The more self-confident among us may have hoped to be leaders of the multitude, but none of us wished to be divorced from it. The generation of Keynes and Lytton did not seek to preserve any kinship with the Philistine. They aimed rather at a life of retirement among fine shades and nice feelings, and conceived of the good as consisting in the passionate mutual admirations of a clique of the elite. This doctrine, quite unfairly, they fathered upon G. E. Moore, whose disciples they professed to be. Keynes, in his memoir 'Early Beliefs' has told of their admiration for Moore, and, also, of their practice of ignoring large parts of Moore's doctrine. Moore gave due weight to morals and by his doctrine of organic unities avoided the view that the good consists of a series of isolated passionate moments, but those who considered themselves his disciples ignored this aspect of his teaching and degraded his ethics into advocacy of a stuffy girls-school sentimentalising.
The tone of the generation some ten years junior to my own was set mainly by Lytton Strachey and Keynes. It is surprising how great a change in mental climate those ten years had brought. We were still Victorian; they were Edwardian. We believed in ordered progress by means of politics and free discussion. The more self-confident among us may have hoped to be leaders of the multitude, but none of us wished to be divorced from it. The generation of Keynes and Lytton did not seek to preserve any kinship with the Philistine. They aimed rather at a life of retirement among fine shades and nice feelings, and conceived of the good as consisting in the passionate mutual admirations of a clique of the elite. This doctrine, quite unfairly, they fathered upon G. E. Moore, whose disciples they professed to be. Keynes, in his memoir 'Early Beliefs' has told of their admiration for Moore, and, also, of their practice of ignoring large parts of Moore's doctrine. Moore gave due weight to morals and by his doctrine of organic unities avoided the view that the good consists of a series of isolated passionate moments, but those who considered themselves his disciples ignored this aspect of his teaching and degraded his ethics into advocacy of a stuffy girls-school sentimentalising.