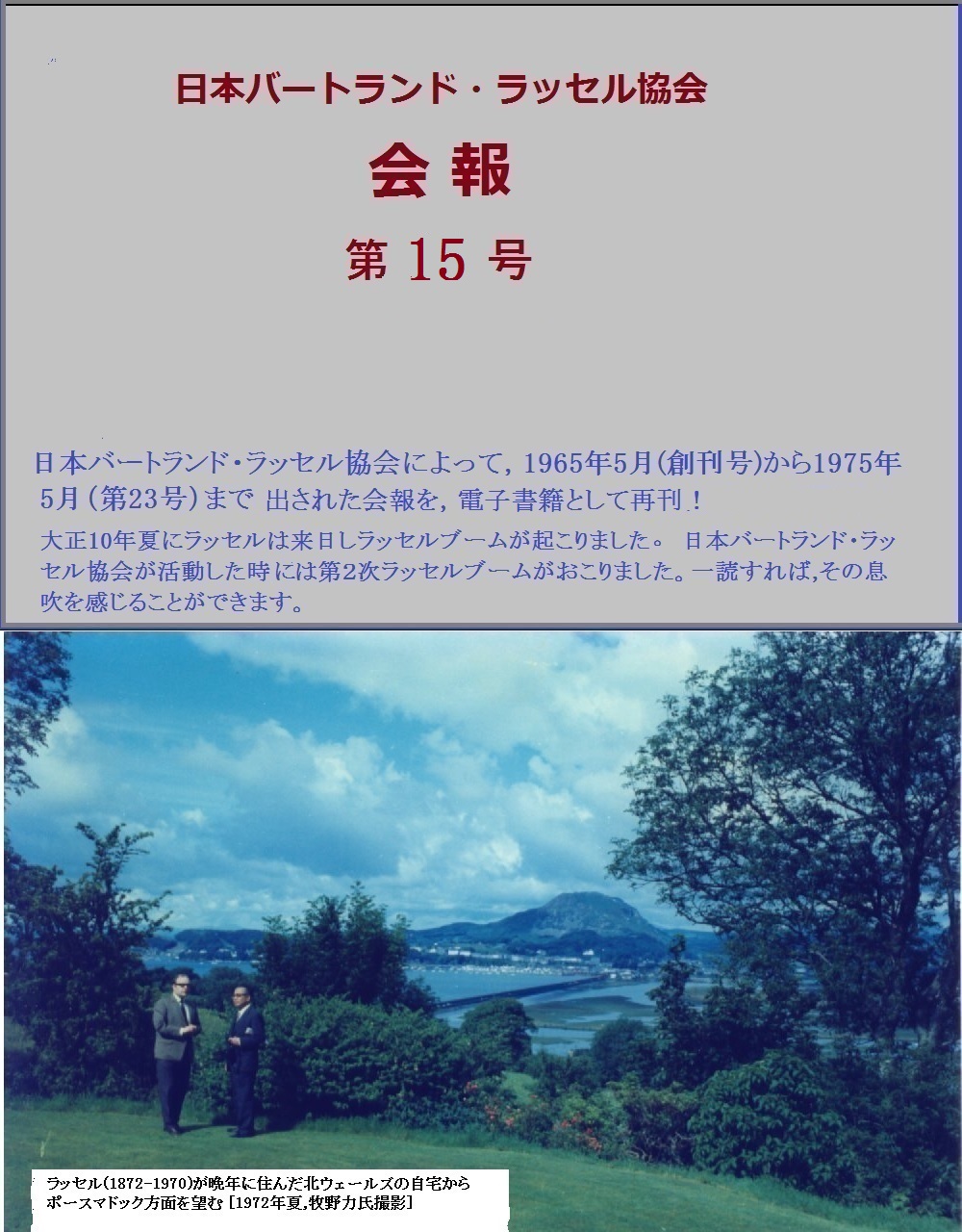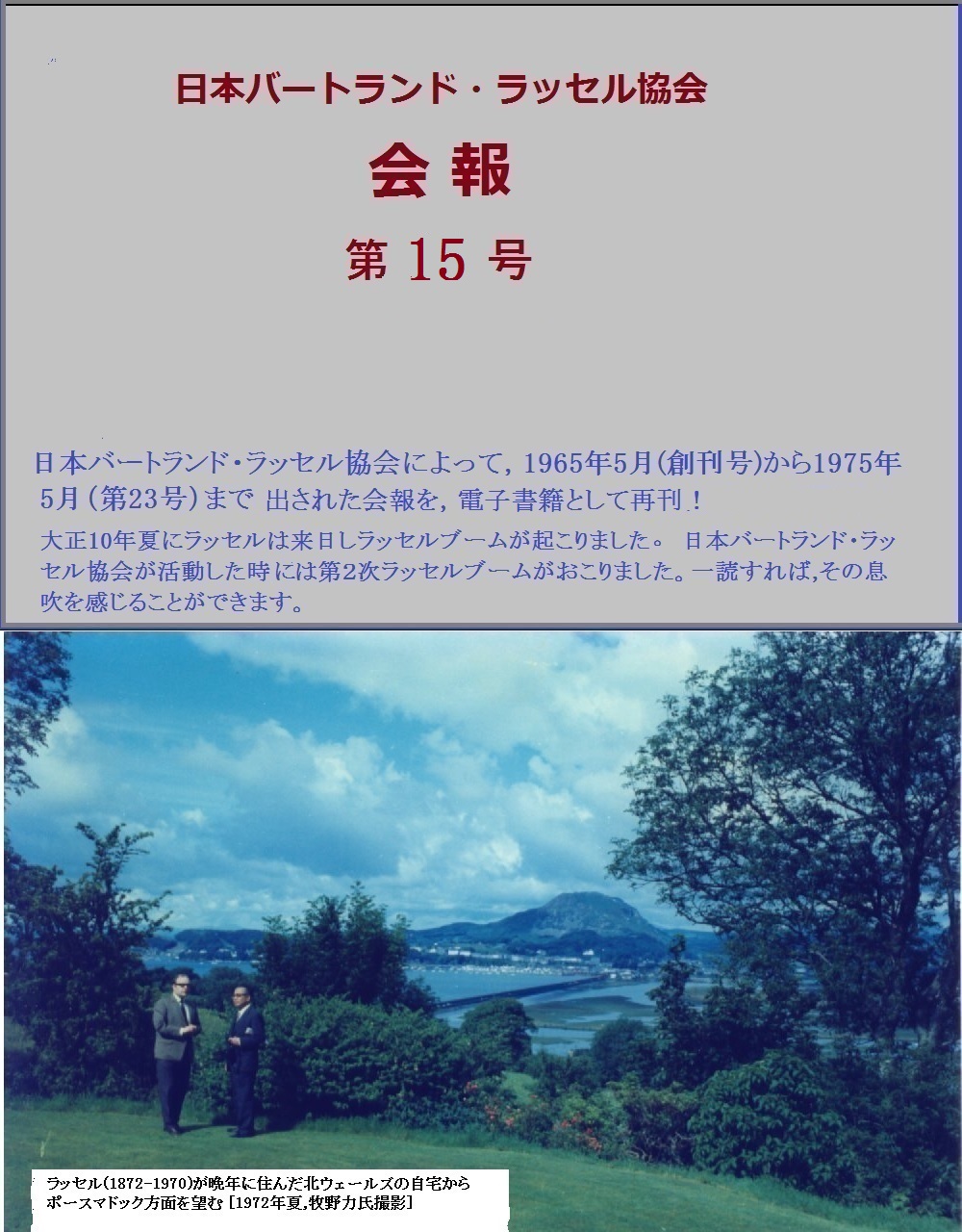加藤将之「バートランド・ラッセルそこのところ」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第15号(1970年5月),pp.6-7.
* 加藤将之氏(1901-1975. 6. 9)は当時、山梨大学教授/東大哲学科卒、文部省図書監修官・日本書籍社員・山梨大学教授を歴任。歌人でもある。
ラッセルは、その尊敬する数理哲学者ライプニッツについて、「かれはいくらか金にけちであった」、と『西洋哲学史』(A History of Western Philosophy, 1945.)のなかで書いている。ハンノーフェル宮延(注:ハノーファー家;ハノーヴァー家)の若い娘たちが結婚する際、王室顧問のライプニッツは、「結婚祝のプレゼント」として、いつも「洗濯をやめてはいけないよ」という「金言」しか与えなかったというのである。『哲学史』のなかで、こういうエピソードをさし込んだラッセルは、ここの所がライプニッツとはちがうようである。ラッセルには、もう少々お色気があった。
ラッセルによれば、ライプニッツの生前に出版された本は、みんな宮廷の王妃あてに書かれたものである。だからそれらは、みんな社交用哲学であり、いい加減なものと見なしてよい。遺稿として残されたものに、本物のライプニッツがある。不朽の価値をもった論理学がそれであるという。
ライプニッツは、女性にはまるで関心のなかった人である。生涯不婚で、浮いたロマンスなど、薬にしたくもない。それをラッセルは、別に問題にしているわけではない。しかし、内心ではおかしく思っていたかもわからない。四度も結婚した経験の持ち主としては、そこの所をラッセルにきいてみたかった気持ちも、わたしにはある。
ところで、こういう生男(きおとこ)のライプニッツについて、その生涯を小説に書いた人がドイツにはある。少し古い本であるが、エグモント・コレルスの『小説ライプニッツ』がそれである。(Egmont Colerus: Leibniz der Lebensroman eines weltumfassenden Geistes, 1934.)
この本については、旧著『哲学者気質』(昭13・第一書房)のなかで紹介したこともあるので、ここで多くを語るつもりはない。ただ、色気も、ロマンスもないライブニッツのような哲学者の生涯でも、これを小説化した人があるという事実を申しあげるだけである。この本のなかには、女性のことは、まるで出て来ないのである。結婚祝に、お金ではなく、金言しかやらなかったという宮廷の紳士のエピソードさえも、くわしくは書いていなかったように記憶している。
そうすると、ラッセルのばあいはどういうことになろうか。将来『小説ラッセル』は、はたして書かれることだろうか。どういうサブタイトルで、それは飾られることだろうか。それをたのしみとして、ほほ笑みをもらすなどは、死者に対する不敬というものであろうか。それとは反対に、人間ラッセルを永久に記録するためには、そのような文芸価値の高い作品も、要請さるべきである- と声を高くして叫ぶのが、ほんとうに、故ラッセル翁を慕う者のとるべき道なのであろうか。いや、ラッセルについては、ライプニッツとは事情がちがう。ラッセルはすでに大冊の自叙伝も書いていることだ、何もかも、そこにはぶちまけている- そうおっしゃる方もあろう。
これも一理がある。ところが、ラッセルの『自叙伝』を読んでみるとき、肝心カナメのところで、ぼかしている個所も、いろいろと目につくように思うがどうか。それを一々、ここに抜き出して申し立てるわけにはいかぬが、彼としては自分では書きにくいこと、遠慮すべきことがらも、かなり多かったのではなかろうかと、わたしには思われるフシがある。
そこらのフシ、アナ、欠け目、クライシスといったものを、具合よく具体化するには、多少のフィクションはあっても、小説的手法に待つのがよいこともあろう。そして、小説の対象としては、わがラッセル一代記の内容資料の豊艶多彩?なことは、誰れしもこれを認めるところであろうと思われる。有力なライターによって、『小説ラッセル』の書かれることを望むものである。
ガラス張りの中の生活みたいに、ラッセルの生涯のことは、すべてはっきりとしている。それにしても、かれのいろいろの転向や変節(例えば、何度かの離婚。また、自由主義教育の実験校をやめたことなど)については、今ひとつきき糺したい所もあるように思われる。そこの所に深くはいりこんでゆける人でなくては、『小説ラッセル』を書くこともむずかしいだろうとは思うのだが。(了)