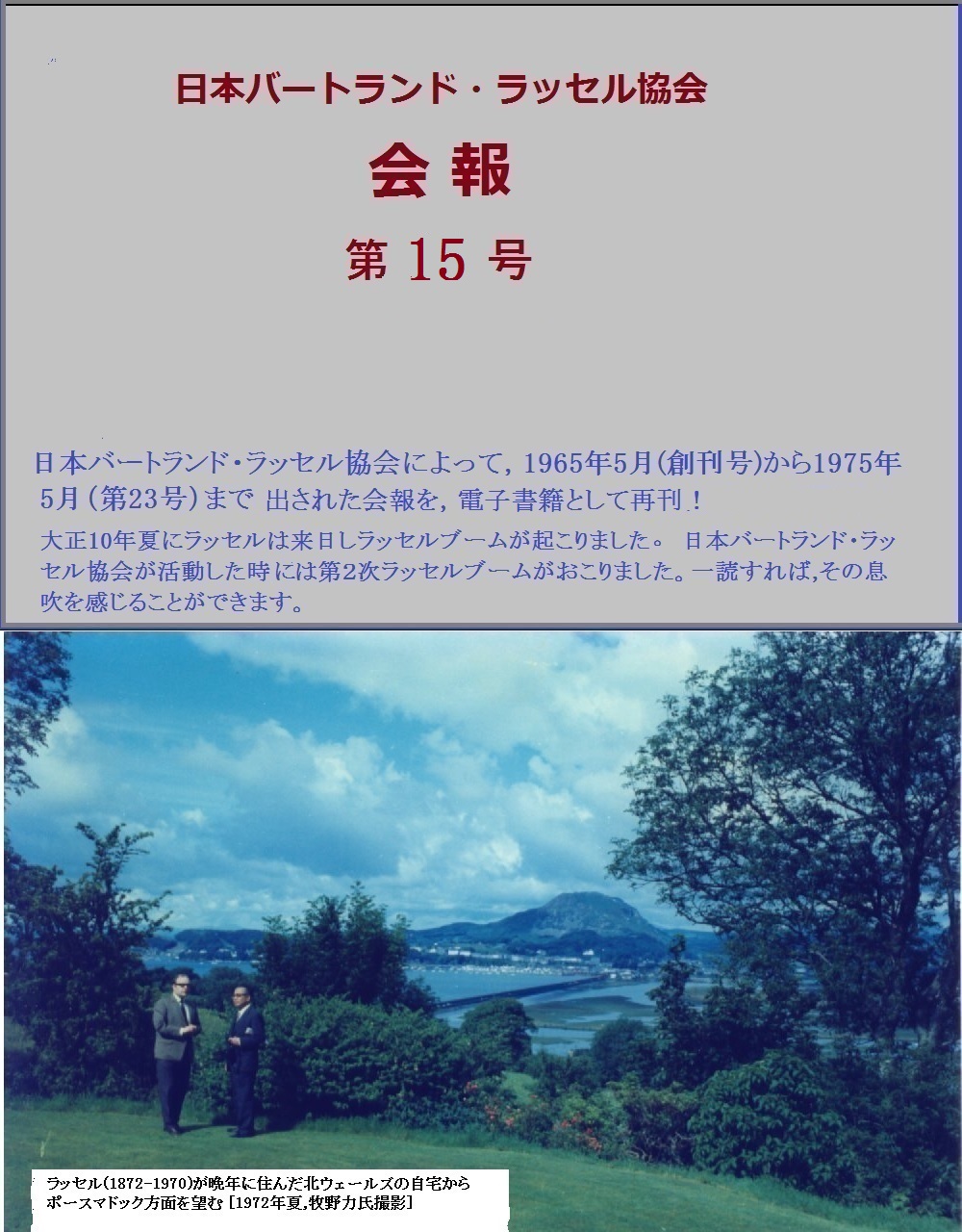(ラッセル追悼) 堀秀彦「バートランド・ラッセルの死を知って」
* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第15号(1970年5月)p.4.
* 堀秀彦(1903-1987.08.28)氏は当時、東洋大学教授、評論家。1972年、学生紛争の続く東洋大学の学長にかつぎだされたが、「私は政治屋ではない」と2年後に辞任。/現在では市販されていないが、(ラッセル著)堀秀彦訳として、『教育論』と『幸福論』がある。
マイアミの空港で、隣りの椅子の上に投げすてられていた新聞(The Evening Star)の2段分の見出しがふと目についた。"Final Plea by Lord Russell urged Israel to End Bombing" 私はほとんど反射的に新聞をとり上げ、ラッセルの死を知った。(1970年)2月4日の午後のことであった。私はその新聞を東京までもち帰った。すてる気がしなかったからだ。ウィルソン首相の言葉がのっている。「ラッセル卿はまさに英国のヴォルテールと呼ばれるにふさわしい。そしてヴォルテールと同じように、彼の会話は彼の著作よりもはるかに素晴しい(brilliant)ものであった。」


楽天ブックスで購入!
|
何年か前に観光旅行者として4日程ロンドンにいたとき、私はいやでもラッセルのことを考えた。私に英会話の能力があって、もしラッセルの話をじかに5分でも10分でもきくことができたら、どんなにステキであろうと空想したことを思い出した。皮肉とジョークと論理とがひとつになった比喩や言いまわしの卓抜な面白さこそ、彼の著作が私を強くひきつけたものであるが、その、面白さをナマに彼の口からきいたとしたら、どんなであったろう! 私はいまこうしたことを空想せずにおれない。イヴニング・スター紙はさらにロンドン・タイムズの言葉をこんな風に伝えている。
「ラッセルこそ最後のほんもののウィッグ党員である。彼の偉大さの一つは、彼が身のまわりの到るところに見出したあらゆる白痴的行為(idiocy)を最後までうけ容れることを拒絶したということだ。」
だとすれば、ラッセルはこの人間の世界の愚かさにとことんまで絶望して亡くなったものであろうか。彼は人類の未来について希望を失わなかったと伝えられているし、彼のどの本文でも、私はそのようなラッセルの考え方をよんだこともある。だが、ほんとうに、彼は人間に、-というよりは、20世紀の人間に希望をつなぎ信頼をもっていたのであろうか。ペシミズムと希望と、この2つの相容れ得ないものが死の直前まで彼のこころのなかでたたかっていたのではなかろうか。
同紙はまた、ラッセル卿の家族スポークスマンの言葉をこんな風に伝えている。
「故人の希望にしたがって、葬式には、一切の花も、一切の行列も、一切の群衆も、一切の儀式(セレモニー)もおことわりする。なきがらは火葬にふせられるが、その灰をどこに撒くかについては、この平和主義哲学者の4番目の妻、レディ・ラッセルがこれを決定するであろう。」
「私が死んだら、屍体は火葬にし、その灰を君の好きなところに適当に撒くんだな。」 生前、彼は妻にこんな風に言っていたものであろうか。だが、それにしても、自分が死んでその屍体が焼かれその灰がどこかにチリヂリバラバラに撒かれてしまうこの自分自身の最後の文字通りの消滅、いや、雲散霧消について、この偉大な哲人は、どんな風なイメーヂをもっていたものであろう。死ねばなにもかもおしまいなのだというどうしようもない人間の事実を、あの冷静無比な頭脳はどんな風に考えていたものであろう?
死ぬ2日前までイスラエルに爆撃を止めよと彼が説いたということは、勿論のこと、この地上からの戦争の廃棄を最後まで希んだということであるが、爆撃を止めよということは人間の生命が何よりも貴重なものであることを前提としたものでなければならない。人間の生命はなによりも貴重なものだ。しかし、その生命の灯が消えたときには、これを灰にし、風と空のなかに、行方知らず、撒布するのだ。-ラッセルの生と死についての考えを、このように、乱暴に、単純化してまとめた場合、この2つのことを、私のようなものにも完全に納得できるように、私はラッセルに教えてもらいたかった。いや、いまも教えてもらいたいのだ。
私は、もしそれだけの時間があったら、死についてのラッセルの考え方を、あのたくさんな著作のなかから、拾い上げ、整理してみたいものだ、と、いまひょいと考える。だが、正直に言って、そうした仕事は、これからの私にはとても出来そうもない。ラッセルの長寿から見れば、今年68歳の私はまだまだ若いかも知れない。けれども、私はラッセルではない。
私は自分の老齢について腹が立ち、ラッセル卿にもう少し生きていてくれたら、そして生と死について、私たちにとっくりと教えてくれる機会があったとしたら、どんなにすてきであろうと、考えずにはおれない。偉大な頭脳も、つまらない人間も、みんなおなじように、百歳にみたぬうちに死んでしまうということが、私には腑に落ちないのだ。(了)